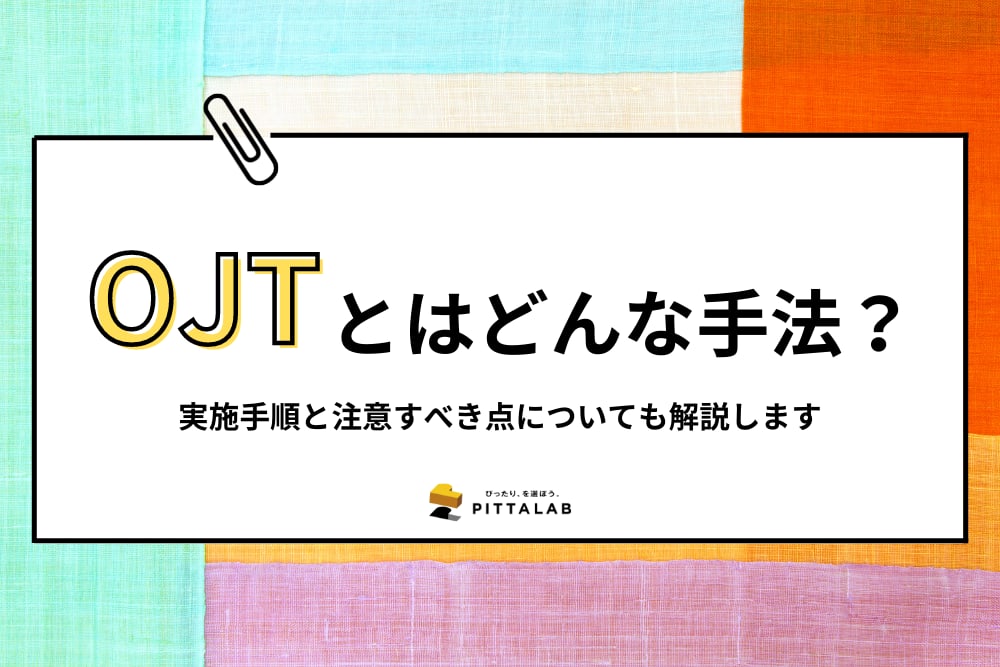OJTとは社員育成などの目的で使用される手法で、即戦力のある社員を生み出す効果が期待できます。OJTとは何か、また、実施手順や注意点について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
OJTの意味は?

OJTとは「On the Job Training」の頭文字をつなげた言葉です。直訳すれば「業務訓練上」や「業務訓練の途中で」となります。
OJTの意味と成り立ち
仕事の際にOJTというと、通常は「職場の中で訓練を行うこと」、あるいは「業務を通して訓練をすること」を指します。OJTとはトレーニングとして特別なことを実施するのではなく、通常の業務を行いながら、必要に応じて上司や先輩社員がアドバイスを行うスタイルのことです。
OJTは、第一次世界大戦中に兵士を訓練する方法として生まれたといわれています。戦争の規模が大きくなるにつれ訓練兵の数も多くなったこと、また、少しでも早く戦力として仕上げる必要があったことなどから、従来のように十分に時間をかけて兵士を訓練することが難しくなったことから、現場で覚えて即実践するOJTが誕生しました。
Off-JTとの違いは何か
一方、Off-JTとは業務とは離れて訓練を行うことをいいます。訓練だけを目的とする研修会を行ったり、講師を招いて知識や業務内容をセミナーで学んだりすることがOff-JTです。
業務を通して普段の仕事内容を学ぶことはできますが、例えば工場での作業中にトラブルが起こったときなど特殊なケースの対処法などは、実際にトラブルが起こってから学ぶのでは遅すぎます。
稀なケースに対しては、Off-JTを通して学んでおくことができるでしょう。また、現在の業務には必要がないけれども将来的に知っておくと良いことなども、Off-JTを通して学べます。
OJTの業務内容の向き不向き
例外が起こりにくい業務とOJTに向いています。例えば、受付業務は、マニュアルが確立されていることが多く誰が教えても差がつきにくいでしょう。このような業務に、OJTは適しています。
一方、予想しにくいことが起こりやすい業務はOJTには不向きでしょう。ある程度の知識やスキルをOff-JTを通して習得してからOJTをするほうが良いと考えられます。例えば顧客の苦情対応など、何を言われるか分からない業務に関しては、ケースごとの対応方法を学んでから実践に移るほうがスムーズな対応を行えるからです。
OJT研修の手順

単に業務を行いながら学ぶことがOJTではありません。OJTを用いた研修ではPCDAといわれる、PLAN・DO・CHECK・ACTIONを用いることが有効とされています。次の4つの手順でOJT研修を実施していきましょう。
【PLAN】具体的な計画を立てる
OJT研修の始めに参加者にとって適切な目標を設定し、計画表を作成します。参加者が研修修了後にどのような状態になることを希望するのかを明らかにするためにも、目標は具体的に計画表内に記し、いつでも確認できるようにしておきましょう。
中間目標と最終目標の2つを定めておくと、計画通りせずに研修を進めていくことができます。また、「慣れる」「上手になる」といったあいまいな目標ではなく、具体的な数字や程度が分かる言葉で目標を定めましょう。
次に、研修全体の計画を立てます。最終目標をいつまでに達成するのかを中間目標に据え、また、どのように最終目標の達成を目指して業務を遂行していくのか、言語化して計画表に書き込みましょう。
【DO】実行する
計画表とは別にスケジュール表を作成し、日付や研修場所、指導担当者、その日の目標、1日のスケジュールを書き込みます。また、管理シートも別途作成し、その日の目標に到達するまでにチェックすべき項目を箇条書きにし、研修参加者や指導担当者がチェックできるようにしておきましょう。
例えば、その日の目標が「パート作業員の管理をスムーズに行うこと」ならば、管理シートには「全員の健康観察を行ったか」「業務前の消毒作業は確認したか」「欠勤者に連絡したか」などをチェック項目として記入することができるかもしれません。
記入するタイミング | 記載内容 | |
計画表 | 研修開始前 |
|
スケジュール表 | 研修中毎日 |
|
管理シート | 研修中毎日 |
|
【CHECK】評価する
次は評価の過程です。1日の業務を終了した後、管理シートを用いて、どのチェック項目が達成でき、どれを達成できていないのかを指導担当者は客観的に判断します。そして、次回にどうつなげていけるのかアドバイスすることができるでしょう。
評価の内容は紙面で残しておきましょう。研修参加者がどのようなアドバイスを受けたのか後で確認しやすくなるだけでなくアドバイスに一貫性があるかをチェックしやすくなり、研修参加者が矛盾を感じずに納得して指導を受けることにもつながります。
【ACTION】改善点を探す
OJT研修の最後は、何が課題として残ったのか、また、どこを改善すればより良い結果につながるのか、指導担当者と研修参加者が話し合う過程です。指導担当者は管理シートを参考にしながら、どのような成果が得られたか、足りない部分はどこかを的確に示します。
指摘した改善点は管理シートに記入しておくと、次回の指導担当者がチェックして新たな計画表作成に活かしやすくなるでしょう。
なお、業務内容によっては、OJT研修中に成果が出るとは限りません。しかし、成果が出ない場合でも、研修参加者が明らかにスキルアップを感じていたり、指導担当者が研修参加者の成長を実感したりしていればひとまずは成功とみなすことができます。
OJT教育の3つのメリット
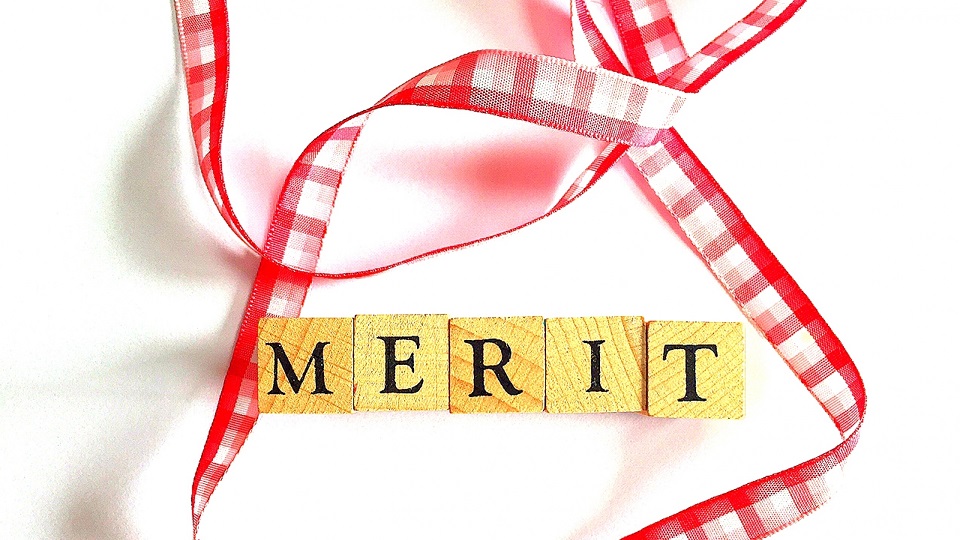
OJT教育を行うことにはいくつかメリットがあります。その中でも代表的な3つのメリットについて見ていきましょう。
1.社員ごとに手法をカスタマイズできる
OJT教育は、PLAN・DO・CHECK・ACTIONの4つの流れで行いますが、どのように実施するかは業務ごとあるいは社員ごとにカスタマイズします。例えば複数の社員が同時にOJT研修を行う場合ならば、管理シートのチェック項目を社員ごとにカスタマイズすることで、社員の特性や改善点に合った研修が実行できるでしょう。
2.即戦力を養える
OJT教育は実際の業務を通して学ぶため、研修を受けると同時に業務を習得することができ、OJT研修が終了する頃には即戦力となっているでしょう。社員教育を行う必要はあるけれども、研修だけ行う時間的余裕がない場合などに、効率よく即戦力を養うためにはOJTの活用が有効です。
3.指導する側も成長できる
OJT研修を行うと、指導担当者も研修参加者の目線で業務を行うことになり、新たな気付きを得られることもあります。また、研修参加者の観察を通して効率的な手法を発見できることがあるだけでなく、自分自身の教え方の改善点も発見できるでしょう。
OJTの注意点と解決法

OJTは優れた研修手法ですが、万能ではありません。OJTを実施する際の注意点とそれぞれの解決法について見ていきましょう。
放置しないようにこまめなフィードバックを
OJT期間の最後に詳しくフィードバックをするだけでなく、できれば毎日評価を実施し、こまめにフィードバックをすることが大切です。OJTはともすれば毎日の作業や評価がマンネリになり、意欲を持って最後まで続けられない可能性がありますが、何度もフィードバックをすることで、研修参加者が意欲を保ち続けやすくなります。
即戦力に差が出ないように指導者は交代制で
指導担当者は交代制にするようにしましょう。研修参加者は指導担当者から学ぶため、担当者自身のスキルに研修参加者の習得できるスキルが影響を受ける傾向にあり、注意が必要です。定期的に指導担当者を変えることで、参加者の戦力に大きな差は生じなくなるでしょう。
最後に

実践を通して学ぶOJT教育は、向き不向きはありますが様々な業界で利用できる研修手法です。特別な準備物も特別な施設も、大幅な追加費用なども掛からないことが、利用しやすさの理由といえるでしょう。
こまめに参加者にフィードバックを与え、指導担当者は交代制にすることで、OJT研修の効果を最大限にする工夫ができます。ぜひ指導者も参加者も成長できるOJT研修を社員育成に活かしていきましょう。