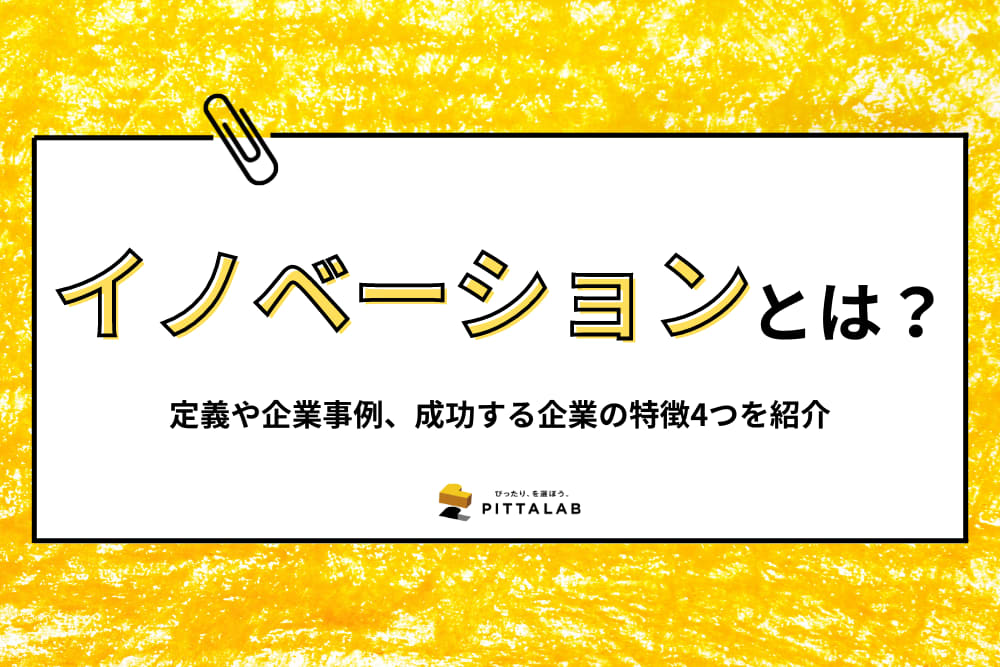新たなアイデアや技術力を取り込むことで、市場や社会に大きな変革を与える「イノベーション(innovation)」は、企業の成長やビジネスの成功において必要不可欠な概念です。
今回は「イノベーションとは」というテーマで、その概要や有名な提唱者の定義、企業の成功事例などについて解説していきます。
イノベーションとは

これからの変革の時代で企業が生き残るためには、新規サービスのリリースやシステムの導入など、様々な角度から常に新たな取り組みへとチャレンジする積極的な姿勢が求められます。イノベーションは企業が成長を続けていく上で、必要不可決な取り組みと言えるでしょう。
イノベーションで有名な3人の提唱者と定義

シュンペーター「5つのイノベーション」
オーストリアの経済学者であるシュンペーターは、1912年に著した代表作『経済発展の理論)』の中でイノベーションの概念を提唱しました。彼は作品の中で企業や経済の発展に欠かせないイノベーションとして、以下の5つのタイプをあげています。
- プロダクト・イノベーション(新しい生産物の創出)
- プロセス・イノベーション(新しい生産方法の導入)
- マーケット・イノベーション(新しい販売先・消費者の開拓)
- サプライチェーン・イノベーション(新しい供給源の獲得)
- オーガニゼーション・イノベーション(新しい組織の実現)
シュンペーターは革新的な新製品・新サービスの開発をはじめとし、会社の生産工程や流通方法、市場開拓、組織体制の変革など様々な観点からのアプローチを提唱しています。イノベーションの成功には、あらゆる視点から企業の経営課題の解決を図ることが重要と言えるでしょう。
クレイトン「イノベーションのジレンマ」
ハーバード大学ビジネススクールの教授であるクレイトン・クリステンセンは、著書『イノベーションのジレンマ』の中で「持続的イノベーション」「破壊的イノベーション」という相反する2種類の定義について提唱しています。
「持続的イノベーション」とは、既存市場の声をもとに、既存商品やサービスをこれまでと同じ方向性で改良するという概念です。安定的に成果を残せるというメリットがある反面、競合企業の革新的な取り組みやアイデアにより売上低下などのダメージを受けやすい、あるいはマンネリ化を引き起こしやすいなどの課題もあります。
「破壊的イノベーション」とは、既存の概念にとらわれることなく革新的なアイデアを積極的に取り入れることで、新製品や新サービスを生み出していく概念です。携帯電話にマルチな機能が備わる革新的なアイテムである「スマートフォン」などは、破壊的イノベーションの代表的な例と言えるでしょう。
また上記の理論とともにクレイトンが課題として提唱したのが「イノベーションのジレンマ」です。これは革新的な技術やビジネスモデルで成功を遂げた企業が、規模が拡大することで革新性を失ってしまう、あるいは新たな技術開発をしても実績に結びつかないなどの状態を表します。
「クローズド/オープンイノベーション
ハーバード大学経営大学院の教授であるヘンリー・チェスブロウは「クローズドイノベーション」「オープンイノベーション」の2種類を提唱しました。「クローズドイノベーション」とは、社内資源だけを取り扱うことで画期的な商品やサービスを生み出すという概念です。
一方の「オープンイノベーション」は外部資源や他業種がもつ技術やノウハウを自社で応用することで、より革新的なアイデアを生み出し形にするという概念のこと。グローバル化や市場の流れが激化した昨今では、自社資源のみに頼らない「オープンイノベーション」に基づいた取り組みが主流となりつつあります。
ドラッカーの提唱するイノベーション

イノベーションのための7つの種
ドラッカーはイノベーションを引き起こすきっかけとして「7つの種(機会)」があることを唱えました。
- 予期せぬ成功や失敗を探す
- ギャップを探す
- ニーズを知る
- 産業構造の変化を知る
- 人工構造の変化を知る
- 意識の変化を知る
- 発明発見をする
例えば「1.予期せぬ成功や失敗を探す」は、日々の業務で起きた想定外の成功や失敗、顧客の要望などを常日頃から記録し、分析することの重要性を定義しています。また「2.ギャップを探す」とは、現状とあるべき理想との乖離を見つけ、その隙間をうめる方法を分析・検討することです。
7つの種は上から順に成功しやすいとされており、7つ目の「発明発見」は最も難易度が高いイノベーションであると提唱されています。
イノベーションを起こした企業事例

今では当たり前のように利用している商品やサービスにも、企業の画期的なイノベーションによって生み出されたものは案外少なくありません。社会や業界に大きな影響を与えた、イノベーションの事例を5つご紹介します。
Amazon(アマゾン)
1994年にジェフ・ベンゾスが創業した「Amazon(アマゾン)」は、Web上の商取引分野で大きな成功を収めた、世界を代表する大企業です。Amazonが成功した要因として「物流センターへの巨額投資」という、これまでのネットビジネスの概念を覆す革新的な行動があります。
本来、在庫や人材確保のリスクを追う物流倉庫の保持は避けるべきとされていましたが、Amazonは自社の優れたIT技術を駆使することであえて自社倉庫を持つことにこだわりました。
これによって「いつ届くかわからない」「在庫切れ」といった従来ネットビジネスの悩みを解消し、今では世界中の人が利用するネット通販ビジネスへと成長しました。
任天堂(にんてんどう)
日本のゲーム業界を引率してきた「任天堂(にんてんどう)」も、過去いくどものイノベーションをゲーム業界に巻き起こしました。
アーケードゲームしか存在しなかった時代に登場した、はじめての家庭用ゲーム機「ファミコン」はゲーム機器の常識を覆す大ヒット商品に。また2006年に発売したゲーム機「Wii」は、体を動かして操作をするという新たな手法が大きな話題となりました。
セブンイレブン
従来アメリカで成功していた「セブンイレブン」のビジネスモデルを、1974年に創業者の鈴木敏文氏が「セブンイレブン・ジャパン」として日本ではじめたのが最初でした。
当時コンビニエンスストアという概念がなく、大規模なスーパーマーケットが主流だった日本で「小規模の小売チェーン店」の登場は画期的でした。また当時大ロットの配送が一般的だった物流業界に、小口配送を実現化したものセブンイレブンでした。
CoCo壱番屋(ココイチ)
カレー業界の最大手である CoCo壱番屋(ココイチ)も、その画期的なアイデアから驚異的な成長を遂げてきました。数ある施策のうち代表的な例として、ドリンクバーの設置と漫画の無料貸出があります。
来客の少ない日中の顧客滞在時間を延ばすことで、新規客が入りやすい空間を実現。新たなファン層の獲得にも繋がりました。回転率が命とされてきたファストフード店の常識を覆す、ユニークなアイデアです。
SONY(ソニー)
日本の音楽業界の最大手であるSONY(ソニー)。1979年に発売された主力商品である「ウォークマン」はイノベーション商品の代表事例です。好きな曲を入れて持ち歩くウォークマンの登場は、それまで据え置きが当たり前だった音楽プレーヤーの常識を覆し、音楽市場に革命を引き起こしました。
イノベーションを起こせる企業の特徴4つ

1.企業のミッション・ビジョンが明確
イノベーションを引き起こす企業の1つ目の特徴として「企業のミッションとビジョンが明確」であることが挙げられます。組織全体がミッション・ビジョンを理解し同じ方向性を見据えることで、長期的な視点から新たな施策やアイデアを打ち出せるためです。逆にこれらが不明確な場合、短期的な成果にばかり注力してしまいイノベーションは引き起こしづらくなります。
2.上下関係なく意見が言い合える
2つ目の特徴は「上下関係なく意見が言い合える」環境です。上下の風通しの良さは、人間関係の悪化を防ぎ、円滑でストレスのない労働環境を実現します。また社内調整の時間を短縮することで、商品開発や顧客の満足度の向上など、イノベーションに繋がる業務へコストをかけることが可能です。
3.トライアンドエラーしやすい社風
3つ目の特徴は「トライアンドエラーしやすい社風」があることです。それまでにない斬新なアイデアを成功へ繋げるには、挑戦と失敗に対する社内理解が必要不可欠といえます。
仮に「絶対に失敗が許されない企業文化」が根付いてる環境であれば、誰も自らイノベーションを引き起こそうとは思わないでしょう。また失敗した社員に対し、再びチャレンジの機会を提供するのも革新を引き起こす会社の特徴です。
4.内部コミュニケーションが活発
4つ目の特徴は「内部コミュニケーションが活発」であることです。社員同士が本音で意見を言い合える文化があれば、新たなアイデアや技術が自ずと生まれやすくなります。また社員の距離感が近いことで、誰かの画期的な提案やアイデアが見逃されるリスクも軽減されるでしょう。
最後に