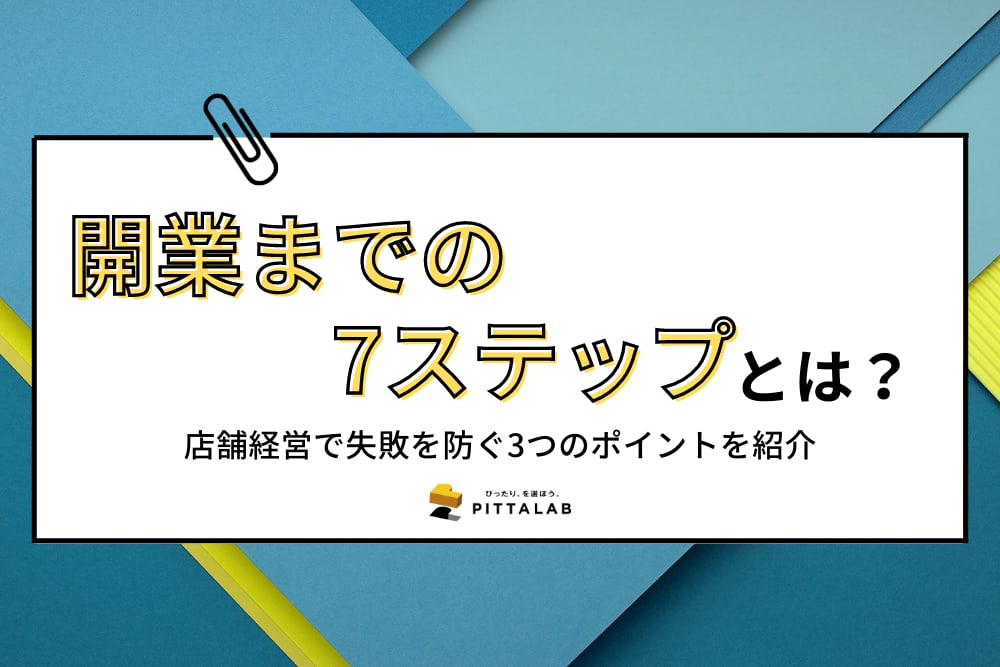「店舗経営の手順について知りたい」「店舗経営をするにあたって知っておくべきことって?」このような疑問を持っていませんか?
この記事では、店舗経営を考えている方に向け、以下を解説していきます。
- 最低限押さえておきたい開業までの7ステップ
- 店舗経営で利用できる国からの助成金について
- 店舗経営を失敗させないためのポイント
記事を読むことで、店舗経営までのステップと、失敗しないためのノウハウを学ぶことが可能です。
開業するためには、まずは開業のステップを知ることからはじまります。記事を読み「店舗経営で成功をおさめるための一歩目」を踏み出しましょう。
最低限押さえるべき開業までの7ステップ

最低限、押さえるべき開業までの7ステップは下記の通りです。
- 開業資金がいくらになるかを確認
- 出店する物件をリサーチ
- 事業計画の作成・立案
- 店舗内の設計・施工
- 国に届け出を提出
- 店の集客方法を考える
- 開店に備えて予行練習
それぞれのステップについて、順番に解説していきます。
1. 開業資金がいくらになるかを確認
まず、開業資金にいくらかかるかを確認しましょう。どのような店舗を運営するかにより、開業資金は大きく異なります。大体の目安として、用意しておきたい資金は「想定している年商の約50%」です。
また、居抜き物件を選ぶことで「厨房設備」「内装工事費」などを安く押さえることができます。設備は、工事の費用は比較的高くなる傾向にあるため、覚えておくとよいでしょう。
具体的な開業資金の使い道は下記を参考にしてみてください。なお、開業資金は、想定年商の50%が適切です、よって、以下では、想定年商2,000万円(合計開業資金1,000万円)とした場合のシミュレーション金額を紹介します。
- 物件取得費:450万円
- 内外装工事費:220万円
- 運転資金:150万円
- 厨房設備:100万円
- テーブル・椅子・食器など:80万円
また、物件取得費用には「店舗の保証金(敷金)」「家賃」の2つが含まれます。店舗物件は、家賃のおよそ8~10ヵ月分が目安となるため、想定する金額より大きくなる可能性が高いです。
さらに、保証金は「費用のうちの35%が償却」といった条件がついている可能性もあるので注意してください。償却とは、借りたお金や投資などを償いとして返すことです。この場合、償却される費用が手元に返ってくることはありません。
開業資金の調達方法は主に2つ
「開業資金が足りないかも……」という人は、下記の調達方法を検討してみてください。
- 日本政策金融公庫から融資を受ける
- 信頼できる親族や知人から借りる
金融機関から融資を受ける場合は、実績がないと難しいです。そのため、最低でも開業資金の1/3程度は自己資金でまかなうのが望ましいでしょう 。
ちなみに実績とは、年商や事業の規模など、事業主として築いてきたこれまでの具体的な成果を指します。
2.出店する物件をリサーチ
次に、出店する物件をリサーチします。物件を選ぶ際は、下記のポイントに注意してみてください。
- 最低でも20件以上は実際に見てみる → 経営が持続している店舗は参考になるから
- 人の行き来が多い立地かどうか → 人の行き来が多い立地は集客しやすいから
- 長期にわたって支払っていける家賃であるかどうか → 固定費が高いと月の収益が伸びにくくなるから
上記の3点は、最低でも押さえておきましょう。
また、出店する物件を決定する際は、どの時間帯にどのような年齢層の人が行き来しているのかも見ておくとよいです。それらを把握しておくことで、集客をする際に具体的な施策が立てられるようになるでしょう。
3.事業計画の作成・立案
融資を受けている場合、事業計画の作成・立案をする必要があることを覚えておいてください。また、事業計画書の売上予測に書く数値は、非常に重要になります。なぜなら、売上予測に書く数値は、融資をする側が一番重要視しているポイントであるからです。
そのため、思いつきの数字ではなく、客観的に見て根拠のある数字を記入しましょう。売上予測に用いられる式は下記の通りです。
売上 = 席数 × 満席率 × 回転率 × 客単価
上記の式を利用して、ランチタイム、ディナー、アイドルタイムなど、時間別に算出しましょう。また、自分の収入をいくら位にするのかを決めておく必要もあります。このとき、収入をあまり低い金額にしてしまうと、外部から融資を受ける際に「この収入では生活できないのではないか?」と疑問に持たれる可能性があるので注意してください。
審査の際に疑問を持たれてしまうと、スムーズな融資を受けられない可能性があります。
4.店舗内の設計・施工
これから運営していく店舗が決まったら、店舗内の設計・施工へと移っていきます。店舗内の設計や施工はとても重要であるため、下記のポイントをしっかりと押さえつつ、慎重に進めていきましょう。
- 厨房はスタッフの動線(動く範囲や道筋)を考慮して設計する
- お客様はもちろん、スタッフが快適に過ごせる環境にする
- 食材の搬入や調理を無理なく行えるかどうか
- 内装費用と外装費用が大きくなりすぎていないか
店舗内の内装については、営業をしている他店舗に訪れて参考にしてみるとよいです。また、店舗の赤字が続き、撤退を余儀なくされた時は、店舗を返さなければいけません。店舗を返す際は、原状復帰を求められる可能性があるので注意してください。
そして、その費用は当然、借手側の負担になるため、仮店舗の場合は、オーナーとよく話し合っておく必要があります。
5.国に届け出を提出
飲食店を開業する際は、国の各種機関へ届け出を提出する必要があります。少なくとも「保健所」「消防署」は必須になりますので、下記を参考に提出を行いましょう。
保健所……店舗の管轄に当たる保健所に「提供するメニュー」「お店の図面」などを提出します。開業前に検査がありますが、事前の相談を必ずしておくようにしてください。
消防署……店舗の管轄にあたる消防署に「消化管理者選任届」「防火対象設備使用開始届」などの提出が必要になります。
また、個人事業としてはじめたばかりの人は「開業届出書」も提出しておきましょう。
6.店の集客方法を考える
お店の準備が整ったら、 集客方法も考えておきましょう。集客方法を考える際は、下記を参考にしてみてください。
- 看板をどこに配置するか
- どの促販ツールを利用するか
- お店と相性の良いSNSはどれか
最低でも上記の3点を押さえておきましょう。促販ツール(チラシ、ダイレクトメールなど)については、事前によくリサーチをしておき、無駄な費用を生み出さないように注意してください。また、 SNSは無料で運用できる広告でもあるため、なるべく早い段階から準備しておくとよいです。
SNS運用は広告としてだけではなく、お客様との関係を構築するためのツールにもなります。有効に活用していきましょう。
7.開店に備えて予行練習
開店の準備が全て整ったら、当日に備えて予行練習をしておきましょう。当日に来るお客様を想定し、開店から閉店までの流れを確かめることが重要です。予行練習をしておくことで、想像していなかった問題点や、すぐさま改善すべきポイントなどが見えてきます。
予行練習を行うのは、スタッフが揃った状態で、開店の約1週間前からはじめるとよいです。少し余裕を持たせておくことで、問題点や改善点が見つかった際、慌てずに対応することができます。
また、新人スタッフのためのオペレーションマニュアルを作成しておくことで、開店後の教育もスムーズになるでしょう。
店舗経営で利用できる国からの助成金

店舗経営を行う場合、国からの助成金を利用できる可能性があります。
- 創業・事業承継補助金
- 小規模事業者持続化補助金
受給できる可能性がある助成金は上記の通りです。以下にて詳しく解説します。
創業・事業承継補助金
創業・事業承継補助金は、新規開業や事業を継承する際、条件次第で受給可能となる補助金です。支給額は「100万円」「200万円」「500万円」の3通りとなっています。原則、
外部からの資金調達を行っていない場合は、100万円が受給額です。
創業・事業承継補助金は、開業後には申請できないため、 条件が合いそうな人は必ず開業前に申請するようにしましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は「ホームページ作成費」「店舗内のバリアフリー化」「広告費」を目的とする、下記事業者が受給対象になります。
- 小売業
- 製造業
- サービス業
補助金の上限額は50万円です。対象となる事業者は厚生労働省にて確認するようにしてください。
店舗経営を失敗させないための4つのポイントとは

店舗経営を失敗させないためのポイントは下記の通りです。
- 接客にこだわる
- 無駄なコストをとことん削る
- 必要な投資はしっかりと行う
- 時代に合わせた経営を行う
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
接客にこだわる
接客にこだわることは、とても重要になります。なぜなら、接客力の向上は低いコストで取り組める上に、再来店の動機につながりやすいからです。
店舗経営では、居心地の良さや料理の質がもちろん重要になりますが、接客の印象が悪いとお客様の再来店率は上がりません。店舗で一丸となり、もう一度来たくなるお店の接客を目指しましょう。
無駄なコストをとことん削る
コストを意識することも大切になります。特に、毎月の固定費用となる「光熱費」「家賃」は重要です。
また、店舗経営の第一関門は「1年目を乗り切ること」だといわれています。そのため、どのような事態でも対処できるよう、運転資金には余裕を持っておきましょう。
必要な投資はしっかりと行う
コストを抑えることも重要ですが、必要な投資はしっかりと行ってください。具体的に、ケチってはいけない投資は下記の通りです。
- スタッフの人件費
- 食材のコスト
特に、人件費をケチらないことは重要です。人件費をケチってしまうと、 離職率が上がり、採用コストが増えてしまう可能性があります。削るべきコストと投資すべきコストの組み分けは明確にしておきましょう。
時代に合わせた経営を行う
どのような店舗も、時代の進化と共にめまぐるしく変化しているため、時代に合わせた経営を行うことはとても重要です。
「どのような料理が美味しいと思われるのか」「お客様はどのような接客を望んでいるのか」など、各々でもとめられることは、時代と共に変化しています。ときには、思い切った経営方針の変更も求められるでしょう。柔軟に対応していく意識が大切です。
事業拡大。多店舗経営のメリットとは

事業拡大にあたり、多店舗経営を考える人もいるでしょう。多舗経営のメリットは、主に、下記にあります。
- 店舗スタッフのやる気アップにつながる
- 仕入値段を改善できる
- お店のブランディングにつながる
それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
店舗スタッフのやる気アップにつながる
店舗数が増えることで、働くスタッフのモチベーションアップにつながります。モチベーションアップにつながる理由は下記の通りです。
- 店舗の成長をじかに感じられるから
- リーダーやマネージャーが増えるから
店舗数が増えれば増えるほど、店舗に求められる役職も増えます。そしてスタッフの一人ひとりが「あそこの役職を狙っていこう」と考えるようになることで、モチベーションが上がるのです。
また、「自分たちの頑張りが店舗拡大に貢献できている」という認識が生まれることで、能動的に働こうとする人も増えるでしょう。
仕入値段を改善できる
多店舗経営をすることで、仕入れ値段の改善にもつながります。なぜなら、仕入れる食料や商品が増えることで、仕入れる際の単価が安くなる可能性があるからです。
仕入れ値段が安くなると、原価率が大きく下がるため、1店舗あたりの利益もかなり向上します。原価率を下げられることは、多店舗経営ならではの、大きなメリットであるといえるでしょう。
お店のブランディングにつながる
多店舗経営をすることで、1店舗ごとのブランディングにも繋がります。なぜなら、 多くの店舗を経営することで「お客様からの人気が高く、 経営に余裕がある」ということを多くの人に知ってもらえるからです。
また、より多くの人に店の名前を知ってもらうことで、店舗の認知度があがり、新規顧客獲得にもつながります。認知度が向上することで、SNSやメディアに取り上げられ、さらに多くの人に知ってもらえるでしょう。
慎重に。多店舗経営のデメリットとは

一見すると、メリットがたくさんある多店舗経営ですが、下記のようなデメリットもあります。
- 初期費用が大きな負担になるリスクがある
- スタッフの管理が難しくなることも
- 経費が高くなりすぎる
それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
初期費用が大きな負担になる?
新店舗の開店にともない、大きな初期費用が負担になる可能性があります。たとえば、
- 陶器や備品の費用
- 物件を取得する際の初期費用
- スタッフを採用する際の人件費
など、新店舗の開設には様々な初期費用がかかります。また、初期費用を計算することも大切ですが「オープンからどれくらいで初期費用を回収できるか」の目安を具体的に持っておくことも大切です。
初期費用の回収が遅れると、他店舗の経営状況にしわ寄せがくる可能性もあるでしょう。したがって、現在経営している店舗の経営状況がうるわしくない場合は、よくよく考えてから多店舗経営へと移行させる必要があります。
スタッフの管理が難しくなることも
新店舗がオープンすると、当然スタッフの人数も増えるため、管理の手間やコストが大きくなります。また、スタッフ一人ひとりとのコミュニケーション不足につながるリスクもあるでしょう。
そのため、多店舗経営をする場合は、事前に下記を決めておく必要があります。
- お店を任せられるスタッフ
- どこからどこまで経営者が介入すべきか
- お店を運営するにあたり必要になるスタッフの人数
最低でも上記を決めておけば、新店舗を開店しても安心です。特に重要視しておきたいのは「お店を任せられるスタッフを誰にするか」という点。任せるスタッフの選定を間違ってしまうと、それだけで経営不振につながるリスクを生みます。
スタッフの経験に加え、周りからの評価や実績を加味し、間違いのない選択を行いましょう。
経費に注意
初期費用や人件費、家賃や光熱費などにより、経費が多くなりすぎてしまうことが考えられます。逆に「2店舗目はうまくいったものの、1店舗目の経営がうまくいかなくなる」といった可能性もあるでしょう。
そういったリスクを回避するための対処法として「店舗を出す立地や、提供する商品のラインナップに変化をつける」という方法があります。1店舗目の経営で学んだことをうまく活かし、2店舗目の経営に役立てる意識が大切です。
また「1店舗目がなぜ成功したのか」だけではなく「失敗した部分」にも目をあて、2店舗目に活かすことも重要だといえるでしょう。
多店舗経営を成功に導く3つのポイント

多店舗経営を成功に導くポイントは下記の通りです。
- 店舗が掲げる理念を明確にしておく
- 経営を任せられる優秀な人材を確保すること
- 撤退ラインをあからじめ設定しておく
成功のポイントを押さえておくことで、失敗のリスクを回避することにもつながります。それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
店舗が掲げる理念を明確にしておく
まず、店舗が掲げる理念を明確にしておく必要があります。理念を明確にしておくことで「接客の雰囲気」「店舗が大切にしてること」などをスタッフに共有しやすくなるからです。
店舗の理念を決める際は、下記のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 従業員全体で共感を生みやすい
- 覚えやすく心に残りやすいものであること
- 具体的で分かりやすいものにする(数字が入っていると尚よい)
上記のポイントを押さえておけば、従業員の共感を生みやすく、現場の士気が上がるような理念が完成します。
経営を任せられる優秀な人材を確保すること
多店舗経営をするにあたり、重要になるのは「経営を任せられる優秀な人材を確保すること」です。また、優秀であることも大切ですが「どのスタッフに任せれば店舗が拡大するか」という経営者としての視点を忘れてはいけません。なぜなら、店舗のタイプによって相性の良いスタッフは異なるからです。
若くてやる気のあるスタッフに店舗を任せることで成功するケースもありますし、経験のあるシニア層に任せることで成功するケースもあります。拡大したい店舗のタイプを見極め、適切な人材を選出しましょう。
撤退ラインをあからじめ設定しておく
撤退ラインをあらかじめ設定しておくことも大切です。一般的に「赤字が3ヵ月続いたら撤退する」といったラインを設ける経営者が多い傾向にあります。
しかし、ただ単に赤字が3ヵ月続いたからといって、撤退するのはあまりおすすめしません。「他店舗の経営状況」「運営資金の状況」などを加味し、複合的に判断する必要があるからです。徹底するか否かの決断は、経営者の手腕が問われているということを覚えておいてください。
とはいえ、潔く撤退をすることで、次のチャンスが生まれることもあるでしょう。たとえ失敗したとしても、その失敗を次に活かせばよいのです。実際、今成功している経営者の多くは、1つ2つのお店を潰してしまった経験を持っています。失敗も成功も、次にどう活かすかが重要なカギであるといえるでしょう。
最後に

一見難しいと思われがちな店舗経営ですか、資金さえあれば、順を踏むことで簡単に開業することができます。ただし、持続させることは容易でありません。
経営の経験がない人であれば、1年間の運営を続けることも簡単ではないでしょう。しかし、店舗経営を見事成功に納めれば、たちまち成功者へ仲間入りすることができます。
経営する店舗が自分の手を離れて、信頼できるスタッフのみで運営できれば、その仕組みから収入を得ることも可能です。これから店舗経営に挑むという人は、入念なリサーチを重ね、万全の態勢でスタートするようにしましょう。