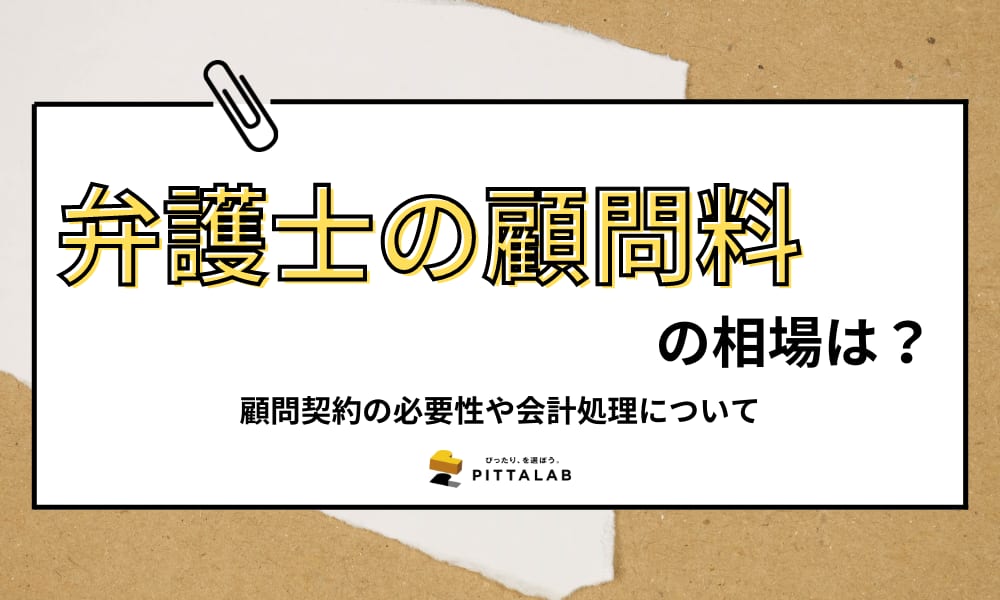中小企業を経営する方で弁護士と顧問契約を結ぶべきか、お悩みの方は多いでしょう。弁護士がバックについていれば、法的なトラブルに見舞われても安心できます。
一方、顧問契約を結ぶ際の懸念材料は顧問料です。「備えあれば憂いなし」だとわかってはいても、顧問料が高額なら顧問契約の締結に二の足を踏んでしまうことも。
そんな状況の方に、本記事では弁護士の顧問料の相場をお伝えします。顧問契約を結ぶ必要性や契約後の会計処理についても触れておりますので、ぜひ最後までお読みください。
法人企業にとって弁護士顧問契約とは

まずは法人企業にとっての弁護士顧問契約の必要性を見ていきます。顧問契約を結ぶと経営上の様々なトラブルについて相談できるので、必要性は大きいです。
また、弁護士にもそれぞれ得意分野があるため、弁護士に顧問契約を依頼する場合は慎重に選定しなければなりません。「〇〇専門弁護士」「△△に強い弁護士」といった広告表現が信用できるかという点にも触れているのでご覧ください。
弁護士の必要性
法人企業にとって、弁護士との顧問契約の必要性は大きいと言えます。弁護士というと法廷で依頼人の弁護をするイメージを持つ方は多いですが、企業にとっての顧問弁護士の役割はそれだけにとどまりません。
経営上、法律に関わるトラブルが発生した際に、会社の味方になって迅速に解決へと導いていきます。例えば、顧客が売掛金を支払ってくれない、消費者から商品・サービスへのクレームを受けた、解雇した従業員が解雇を不服として訴えを提起した、など経営上直面するトラブルの内容は様々です。
こういったときに、顧問弁護士がいればトラブルの相手方との交渉を代行してくれるので、スムーズに事が進みます。また、労働基準法や会社法、特定商取引法など会社が経営上守らなければならない法律は数多いです。創業時からこれら全ての法律を完璧に守って事業を進めている企業はほとんどありません。
顧問弁護士がつけば、長期的に継続して法整備の変革を進め、会社を健全な体制へと導いてくれるでしょう。例えば、就業規則は創業時から同じものを使用しており、現在の法制に則っていないという企業も少なくありません。こうした法整備に関する抜け落ちを指摘し、誤りを正すことも顧問弁護士の重要な役割です。
さらに、顧問弁護士には経営者の良き相談相手としての一面も。会社経営では資金調達や事業の拡大・縮小、業務提携の可否など、重要な決断・判断が必要なケースに直面します。こうしたときに数々の経営者の相談に乗ってきた弁護士であれば、適切なアドバイス・助言をくれるでしょう。
このように、顧問弁護士の幅広い業務範囲や経営者の「良きパートナー」となりえることは顧問契約を検討する際の大きな判断材料と言えます。
多様化する取引形態
企業が行う取引形態は複雑かつ多様化しており、従来のひな形を用いた契約書作成が通用しなくなってきました。
また、そもそも契約書のひな形はどんな契約内容にも当てはまる一般的な内容しか記載されていないことが多いです。疑義が生じるような箇所は「当事者で協議する」などという文言でぼかされていました。
顧問弁護士に依頼すれば、契約内容を適切に反映し、具体的な契約書を作成してくれます。また、当事者の力関係なども考慮し、こちらに有利に働くような条項を定めることも可能です。
契約条項もひな形と比べ極力明確に作成してくれるため、契約書に定めがないことが原因のトラブルを回避できます。企業が取引先と交わす契約書は、秘密保持契約書や金銭消費貸借契約書、売買契約書など様々です。
特に事業規模が大きくなるほど全ての契約書を自社でチェックするのは難しくなるので、顧問弁護士の力を借りた方が良いでしょう。
弁護士にもそれぞれ得意分野がある
弁護士にはそれぞれ得意分野があるので、弁護士であれば誰でも良いというスタンスで顧問弁護士を探すのは避けるべきでしょう。例えば、ベンチャー企業の顧問弁護士を見つける際に、相続に強い弁護士を選定しても、IT法務について適切なサポートを受けられない可能性があります。
では、自社の事業範囲とマッチする弁護士を見つけるためにはどうすれば良いのでしょう。ネットで「〇〇(業種名) 弁護士」のワードで検索をかけると、「〇〇に強い弁護士」「〇〇専門弁護士」などの謳い文句が書かれた広告を発見することがあります。
しかし、こうした謳い文句をそのまま鵜呑みにするのは危険です。「〇〇に強い弁護士」「〇〇専門弁護士」という広告表現は、それぞれの弁護士事務所が自己申告しているに過ぎません。
医者ならば「〇〇専門医」と言えば各分野のスペシャリストだと判断できますが、弁護士の業務範囲は学術的な分類がされておらず、グレーな側面が大きいです。したがって、「〇〇に強い弁護士」と書いてあっても、他の弁護士よりもその方面で優れていることを意味するとは限りません。
顧問弁護士を選定する際はこの点に注意し、広告表現を鵜呑みにせず、口コミやHPに書かれる経営理念なども参考に、多面的な判断をおすすめします。
気になる弁護士費用の相場はいくら

顧問弁護士をつけたら報酬にいくらかかるのか気になる、という方は多いでしょう。ここでは弁護士費用の相場を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
弁護士の顧問料の相場
日本弁護士連合会が弁護士に行ったアンケートによると、中小企業と契約する際、顧問料の相場はだいたい月額3~5万円になるようです。ただし、この金額はあらかじめ契約で定めた業務に対してのみとなる点に注意してください。
定額の場合が多いため、契約で定められた内容であれば期間内に何度依頼しても同じ料金ですが、契約に含まれていない業務を依頼する際は別途料金が発生。また、定額制なので業務を一度も依頼しなかった月でも費用は発生します。
固定費が月3~5万円程度増えるのは資金繰りが厳しくなりがちな中小企業にとって大きな負担となるでしょう。とはいえ、弁護士という強い味方が得られることは想像以上にメリットが大きいので、これだけの費用を投じる価値はあると考えられます。
弁護士と契約するメリット・デメリット

顧問弁護士と契約を交わすか判断する際はメリットとデメリット、両方を考慮して決定することが重要です。デメリットもきちんと把握しておけば、後になって「思っていたのと違う!」と後悔する可能性が低くなるでしょう。
ここからは弁護士と顧問契約を交わす際のメリット・デメリットを紹介しますので、ぜひ判断の一助にご活用ください。
メリット
弁護士と顧問契約を交わすメリットには以下の点が挙げられます。
- トラブルに対応するための時間や労力を節約できる
- 何かあった際にその都度弁護士を探す手間が省ける
- 困った時に相談相手がいるという安心感が得られる
- 即座に顧問弁護士に連絡を取り、対応方法などを聞ける
- 自社の状況を考慮した、適切なアドバイスをくれる
- 問題が大きくならないうちに解決できる
- 経営者が事業の推進や経営に集中できる
先に紹介したように、顧問弁護士はトラブルの相手方と直接やりとりしてくれるので、経営者自身が対応する必要が無くなります。また、会社に生じた全てのトラブルは基本的に顧問弁護士に一任するので、トラブルの内容に応じて弁護士を変える必要もありません。
心理的な支えになるという側面も大きいです。経営者は孤独な判断を余儀なくされますが、顧問弁護士がつけば全ての事柄を自分だけで判断するプレッシャーから解放されます。
これまで様々な困難を乗り越えてきた自負があっても、未知の状況で迅速な判断を迫られるようなケースに直面すると、たとえ百戦錬磨の経営者であっても足がすくんでしまいがちです。この点、法律の専門家が常にバックについていれば、大きな安心感を得られます。
アドバイスもどこの企業にも当てはまる一般的な内容ではなく、会社が直面する状況やこれまでの経緯も含めた顧問弁護士特有のオーダーメイドされた意見をもらうことが可能です。このため、ネット検索では得られない、正しく的確な解決策を提案してくれるでしょう。さらに、気がかりレベルの小さなことでも相談するように心がけていれば、トラブルの芽を未然に摘むことも可能です。
このようにメリットが多い顧問契約ですが、最大のメリットは経営に集中できるという点にあるかもしれません。どんなに優秀な経営者でも一人でできることには限界があります。法的な問題は専門家である弁護士に任せることで、経営者は企業経営に集中でき、会社の安定した成長につながるでしょう。
デメリット
先ほどもお伝えしましたが、顧問弁護士の唯一かつ最大のデメリットは費用面の負担が大きくなる点にあります。とはいえ、毎月3~5万円程度の顧問料であれば費用が増加すると言っても、そこまで大きな負担にならない会社も少なくないでしょう。
費用面については会社規模や財務状況に左右される部分ですが、上述したように数多くのメリットがあることを考えると甘んじて受け入れた方が良いケースもあります。
顧問料が定額制であっても、訴訟対応などイレギュラーな業務依頼は別途費用が発生する可能性が高いですが、その場合でも顧問契約を結んでいる会社には割引を利かせてくれる法律事務所もあるようです。さらに、顧問契約を結んでいればその弁護士が抱えている他の案件より優先して対応してもらえる場合も。
注意すべき状況を一つ挙げるのであれば、利用頻度が少ないケースです。弁護士をほとんど利用しないにも関わらず、毎月顧問料が発生する状況は無駄なコストが生じていると言わざるを得ないでしょう。
ただし、弁護士によっては定額制ではなく利用した時間分だけ費用が発生するタイムチャージ制を採用する場合もあります。自社に適した料金体系を取る弁護士に依頼すれば節約につながりますので、弁護士選びの際は費用面についてしっかり確認するようにしましょう。
契約後の会計処理について

中にはすでに弁護士と顧問契約を交わしている会社もあるでしょう。現在契約中の会社が抱きやすい疑問は、会計時の処理をどう行えばよいのかという点になります。
特に弁護士への顧問料支払い事務をはじめて担当する社員にとっては、頭を悩ませやすい点でしょう。弁護士への顧問料支払いにおける会計処理のポイントをまとめましたので、ぜひご覧ください。
源泉徴収する?しない?
弁護士に対する報酬は源泉徴収が必要かという点は疑問を抱きやすいポイントです。源泉徴収とは、報酬を支払う際に取引先が納めるべき所得税の額を控除し、取引先の代わりに税務署に納める制度となります。
企業がフリーランスや個人事業主に外注する際は、原稿料など一定の種類の報酬を支払う場合には基本的に源泉徴収を行わなければなりません。肝心の弁護士に対する報酬はどうなのかという点ですが、弁護士への報酬も源泉徴収が必要です。
所得税法204条において、弁護士の業務に対する報酬を支払う者はその支払いの際に源泉徴収を行い、徴収した月の翌月10日までに国に徴収した所得税を納めなければならないと定められています。
つまり、会社にとっては弁護士と顧問契約を結ぶことで、毎月の報酬から源泉徴収し税を納める義務が生じてしまうのです。このように、事務作業が増えてしまうことになる点は覚えておきましょう。
ちなみに源泉徴収が必要なのは、報酬の支払い者が法人の場合だけです。依頼主が個人であれば源泉徴収の必要はありません。
着手金と報酬金の違い
通常、弁護士に対して支払う報酬には「着手金」と「報酬金」の2種類があります。着手金とは業務を依頼した時点で支払いが必要な費用のことで、報酬金とは業務が終了した時に支払い、成功の度合いに応じて金額が変わる特徴がある費用です。
基本的に顧問弁護士へ支払う顧問料は法律事務所で定められた金額を毎月支払う定額制の報酬体系となります。そのため、着手金や報酬金というものは存在しません。しかし、業務範囲外の単発の仕事を依頼すると着手金や報酬金の支払いが発生する場合があります。
例えば、売掛金(いわゆるツケ)の回収を依頼した場合、日本弁護士連合会が行った調査によると、顧問弁護士に依頼した際の相場は着手金が約60万円程度、報酬金が約150万円程度になるようです。基本的には着手金よりも報酬金の方が金額は大きくなります。
業務範囲外の仕事を顧問弁護士に依頼した場合、着手金と報酬金、2度の支払いが必要となる点は知っておく必要があるでしょう。
契約期間中の顧問料を前払いした場合
顧問料を1年分前払いすれば、その金額を全額経費に算入できるので節税になると聞いたことがある方もいるかもしれません。確かに「短期前払費用の特例」を適用することで、一定の条件をクリアした前払い費用は、支払った年度の経費として扱うことができます。
しかし、全ての前払い金がこの制度を利用できるわけではなく、残念ながら弁護士への顧問報酬は適用外です。つまり、弁護士の顧問報酬を年度当初に一括前払いしても、節税効果を得ることはできません。
禁止されているわけではないため、一括払いしたければしても良いのですが、本来払うべき金額を早く支払っただけで特にメリットはないことになります。
弁護士顧問料が発生したらやるべきことは?

最後に、弁護士顧問料が発生したらやるべきことを解説します。
年始に支払調書を提出
弁護士に対する報酬を支払った際は、翌年のはじめに支払調書を税務署に提出しなければなりません。支払調書は、会社が個人に対して業務を依頼し報酬を支払った際に、その金額と源泉徴収税額を税務署に申告するために必要な書類です。弁護士や税理士に対する報酬については、その年の支払い総額が5万円を越えるケースで支払調書の発行が求められます。
支払調書の提出義務者は「源泉徴収の義務がある者」となっているので、弁護士の報酬に対して源泉徴収を行っていた会社がしなくてはなりません。支払調書の提出期限は翌年の1月31日までですので、忘れずに提出するようにしましょう。
提出期限までに支払調書を提出しないと、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。
最後に

弁護士への顧問料の相場や、顧問契約を結ぶメリット・デメリット、契約後の会計処理について解説してきました。弁護士の顧問料の相場はだいたい月3~5万円となります。
弁護士の顧問契約は、自社に適した契約書の内容を考えてもらえる、経営者が安心して事業に専念できるなどメリットは多くある一方、デメリットは費用がかかることの1点のみです。
弁護士と顧問契約を結ぶことについて悩んでいる経営者の方は、まずは法律事務所に問い合わせをすることからはじめてみましょう。