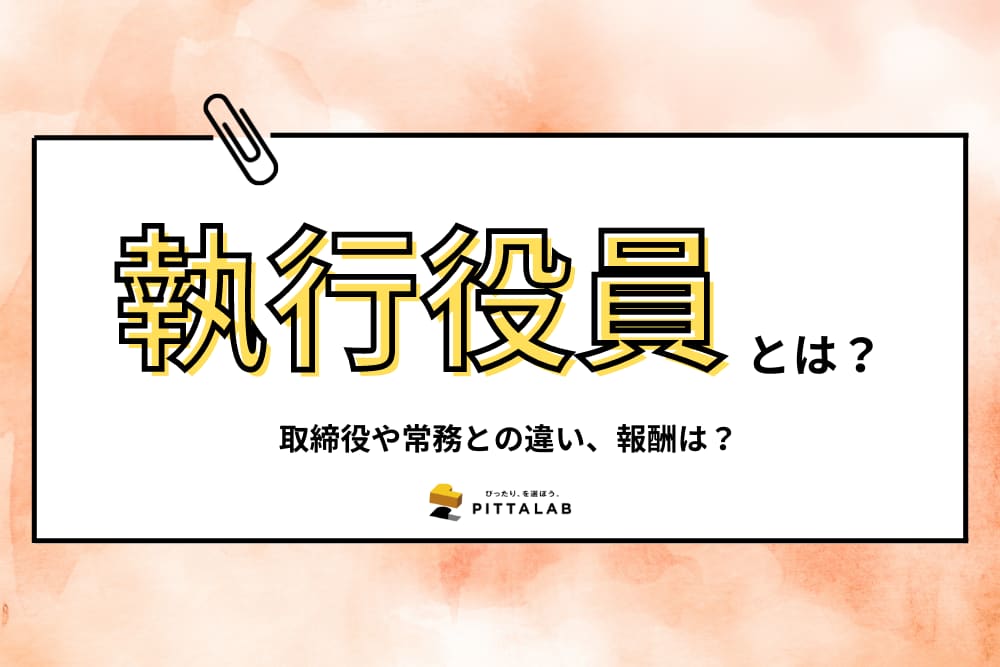執行役員とは、事業運営の事実上のリーダーです。取締役会で選任され、会社の方針に沿って事業を進めていくという役割を担います。役員とは何が違うのか、また、気になる報酬についても見ていきましょう。
執行役員とは?

会社の運営方針を決定する権利はないものの、実務における責任者としての立場にあるのが「執行役員」です。取締役会の決議で選任されて、会社の方針に従って業務を推進していきます。執行役員は社内でのみ有効な役職ですが、名刺に記載することは可能です。
取締役との違い
会社経営において重要事項を決定する立場にあるのが「取締役」です。株式会社において取締役は少なくとも1名以上必要で、株主総会の決議を通して選任されます。一方、執行役員は株主から選任を受ける必要はありません。
また、取締役は会社の外部から選任されることがあります。その場合は、透明性の高い経営を実施できるという効果も期待できるでしょう。
常務との違い
「常務」は会社のトップである社長を補佐する立場です。また、サポート業務だけでなく、事業運営を行うため、幅広い業務に従事します。常務は取締役のように株主総会で選任される必要がなく、なおかつ人数についても決まりはありません。
役員との違い
経営陣を「役員」と呼びます。会社法では取締役や監査役、会計参与を指して役員といいますが、これら三役に入らない立場であっても経営陣であれば役員と呼ぶことが一般的です。
一方、執行役員は、名刺には「執行役員」という役職名を乗せることができますが、職業を問われたときは「会社員」や「従業員」となります。そのため、元々役員である人が執行役員を兼任しない限りは会社経営に携わらず、役員を名乗ることもできません。
執行役との違い
「執行役」は指名委員会等設置会社内での役職で、法律によって1人または2人以上設置することが決められています。
なお、役員と兼任していない執行役員は基本的には従業員ですが、執行役は従業員ではなく役員です。そのため、会社の経営において重要なことを決定する立場にあります。
執行役員について知っておきたい3つのこと

取締役会での決議により選任されると、執行役員になります。株主総会で選任を受ける必要がないため、現在の立場に関係なく誰もが執行役員になる可能性があるといえるでしょう。執行委員について最低限知っておきたいことを3つ紹介します。
1.経営効率向上のために作られた立場
執行役員を任命することで、実務は執行役員、経営は取締役などの役員と業務分担をすることができます。一人にかかる業務や責任が減り、それぞれ自分の役割に専念できるため経営効率を向上させることができるでしょう。
また、執行役員は従業員として現場を把握しているため、現場の声を反映した意思決定ができます。経営の機動性と妥当性を高めるためにも、執行役員を配置することは優れた方法といえるでしょう。
2.優秀な人材の能力を活かせる
取締役会の承認さえ得られれば執行役員を選任できるため、取締役などの役員になるにはまだ早い若い社員であっても、実力さえあればその才能を活かすことができます。現場でリーダーシップを発揮している課長・係長クラスの社員や、優れた実行力を有する若手社員も、序列に関係なく任命することができるでしょう。
また、今後、役員に取り立てるか迷っている社員を執行役員に任命し、実力のほどを試すこともできます。なお、執行役員は原則として任期は1年なので、実力を見て、延長することもできるでしょう。
3.役員報酬はつかない
執行役員は「役員」という名前はつきますが、経営に対して決定権を持っている本当の意味での役員ではないので、役員報酬を受け取りません。取締役などの役員を兼任している場合は役員報酬を受け取りますが、あくまでも本来の役員職に対しての報酬であり、執行役員をしていることに対する報酬ではないという点に注意が必要です。
役員職を兼任していない執行役員は、役職はつくものの一般の従業員と何ら変わりはありません。とはいえ、執行役員に任命される以前より仕事も責任も増えることになりますので、社内の規定に沿い、賞与などの形で相応の報酬が支払われる可能性はあります。しかし、幹部が期待したような結果を出せていないときは、必ずしも賞与や給与が増えるとは限りません。
執行役員制度とは

通常の役員とは別に機動性の高い執行役員を配置する「執行役員制度」は、元々はソニーで誕生した制度とされています。経営と実務の両方を役員が担当すると不正が起こりやすくなるため、執行役員制度を導入し、経営と実務のトップを分離したのです。執行役員制度は他の企業でも導入され、社内の不正防止に役立っています。
また、経営不振時には、役員が担当する業務に負荷がかかり、経営を守ろうとするために会社の根幹を成す実務がおろそかになるなどの本末転倒の事態が生じかねません。場合によっては、役員によって粉飾決算などの不正が起こる可能性もあるでしょう。
そのような会社の危機に際しても、執行役員制度は役立つ制度です。実務を従業員の中から選んだ執行役員が担当し、役員は経営のみに専念することで、実務を確実に進めながら経営の立て直しを図ることが可能になるでしょう。
さらに社内の透明性を保つために、役員内に第三者的存在を置くこともできるかもしれません。会社以外から取締役を呼び寄せ、不正が起こりにくい組織を構築することもできます。
最後に

執行役員は、役員ではなく従業員としての立場を活かした実務のトップです。経営のトップは役員などの経営陣が担当し、実務のトップは従業員から選任された執行役員が担当することで、経営においては透明化が実現するだけでなく、実務においては機動性の向上を期待できます。
また、執行役員は取締役会でさえ承認されれば任命できるため、実力はあるけれどまだ役員には早い課長・係長クラスの社員や若手社員を選ぶことも可能です。社内不正の抑止力にもなるので、ぜひ執行役員制度の導入を検討してみましょう。