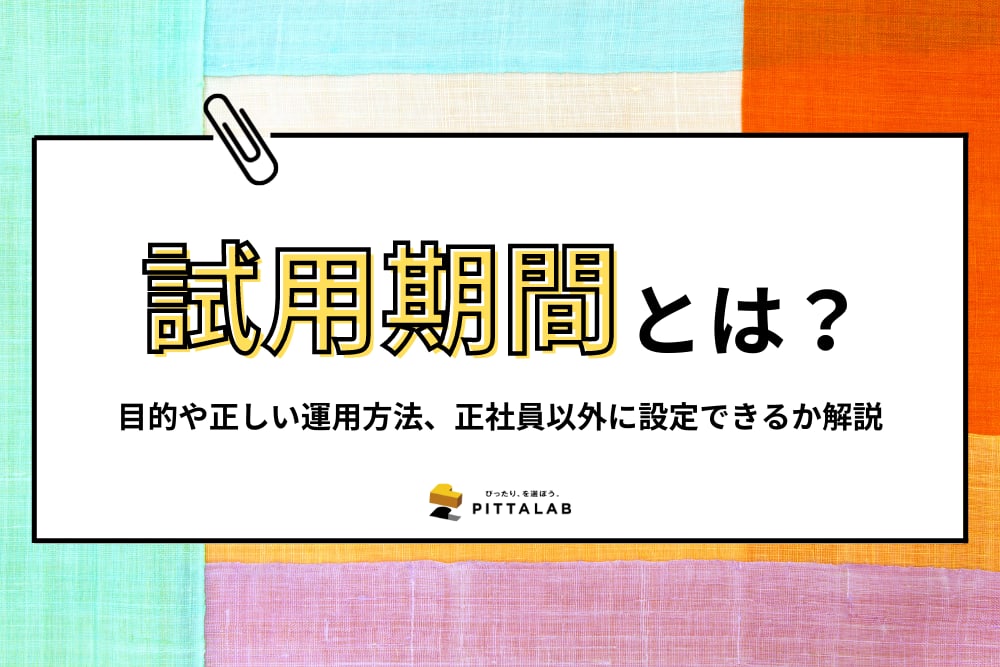試用期間とは、新規採用者を最終的に雇用するかを判断する一定の期間を指します。自社の社員として適性があるか、実務のなかで判断しようとするものです。
本記事では、試用期間の目的や労務管理、本採用拒否の場合の対応について紹介しましょう。
試用期間とは?

試用期間は、どのような目的で設けられているのか、日数はどのくらいなのかについて見ていきましょう。
試用期間を設ける目的
試用期間を設けるのは、実際に労働に従事してみて仕事への適性があるか、勤務態度は良好かを確認することが目的です。採用試験における書類選考や面接だけでは、社員が自社に合う人材かどうかを見極めるのが難しい場合があります。
社風が合わないなど入社後のミスマッチにより早期退職してしまう新入社員も少なくありません。そのようなことを避けるためにも、試用期間を設けてしっかりと適性を判断したいという使用者側の意図があるのです。
使用者と社員の間には解約権留保付労働契約が締結され、解約権の留保はあるものの雇用契約が成立しています。一般的な社員と同様、適切な取り扱いがされなければなりません。
試用期間の日数
試用期間の日数については法律の定めがなく、会社の裁量に委ねられています。しかし、無制限な裁量が認められているわけではなく、社員の適性を判断するために合理的な期間を設定しなければなりません。
試用期間は社員にとって解雇の可能性がある不安定な期間です。長すぎては合理性を欠き、短かすぎては適性をしっかり判断することができないでしょう。合理的といえるのは3〜6カ月の範囲で、一般的には3カ月程度の期間が設けられています。
パートやアルバイトでも設定できる?
試用期間は雇用形態に関係なく設定できます。パートやアルバイトに設定しても問題ありません。期限の定めがある場合は、期間満了後に契約を更新するかどうかの判断ができるため、特に試用期間を設ける必要はないでしょう。
しかし、雇用の期間を定めていない場合、パート・アルバイトも正社員と同じく適性を判断するために試用期間を設けることがあります。ひとつの会社で雇用形態の異なる社員を採用している場合、それぞれ違う期間の試用期間を設けることがあるかもしれません。そのような設定をする場合、就業規則に記載してあらかじめ社員に周知させる必要があるでしょう。
試用期間中に注意したい2つの労務管理

試用期間でも労働契約が締結されるため、各種社会保険や時間外労働などは一般の社員と同じように扱わなければなりません。労務管理には注意しましょう。
1.各種社会保険への加入義務
会社は労働契約を締結した場合、一部の短時間社員を除き、社員を各種社会保険に加入させなければなりません。加入義務のある社会保険は以下の通りです。
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
社会保険加入の義務がないのは、短期アルバイトなど契約期間が2カ月以内の有期契約である社員です。試用期間は本採用を前提とした雇用契約であるため、試用期間の開始から加入が必要になります。試用期間を開始する社員には、トラブルを防ぐ意味でも労働条件を記載した「労働契約書」を発行するようにしてください。
2.時間外労働の扱い
試用期間中の社員が時間外労働や休日労働を行った場合、他の社員と同じく時間外労働の割増賃金を支給しなければなりません。試用期間だからと残業代を払わないのは違法です。
また、試用期間中の賃金を本採用後の賃金よりも低く設定することに問題はありません。しかし、各都道府県の最低賃金を下回らないよう注意してください。
試用期間経過後に本採用になった場合、試用期間が賞与の査定期間に含まれるかという問題もあります。こちらは法律の規定がなく、査定期間に含めなくても特に違法ではありません。
一方、有給休暇の付与条件には試用期間も含まれるので気をつけましょう。労働基準法では有給休暇付与の条件として、「6カ月間の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」を規定しています。試用期間は6カ月間の継続勤務に含まれ、本採用後の勤続日数と合わせて計算しなければなりません。
試用期間中の解雇や本採用拒否する場合

試用期間では、解雇や本採用拒否を検討することもあるでしょう。その際は、従業員とのトラブルにならないよう、慎重に行う必要があります。
解雇する場合の要件
試用期間だからといって、簡単に解雇できると考えるのは間違いです。解約権は留保していても労働契約を締結している以上、一般の社員と同じく解雇は慎重に行う必要があります。就業規則に解雇について明確な記載があり、社会的に相当な方法で行われなければなりません。
解雇の要件は、試用期間開始から14日以内と14日を超えた場合とで異なります。14日以内であれば解雇の予告なく解雇ができますが、14日を超えている場合は通常の解雇同様、30日前に社員に対する解雇の予告が必要です。14日以内の解雇であっても自由に解雇できるわけではなく、合理性と社会相当性の要件に当てはまる必要があることに変わりありません。
解雇を行う場合は、就業規則に解雇事由が明記され、それに沿って行う必要があります。その際に要求される合理性と社会的相当性が認められるのは、一例として次のような事情がある場合です。
- 正当な理由なく欠勤や遅刻を繰り返す
- 求められる職務の能力に達しない
- 業務に意欲がなく上司の指示にも従わない
- 他の社員と協調する様子がない
- たびたび暴言を吐いた
- 履歴書の記載内容に虚偽があった
- コンプライアンス違反を行った
このような事情がある場合でも、社員と話し合うなど改善のための指導を行うなど努力が必要になります。試用期間満了後に本採用を拒否する場合も、当然のように拒否できるとは限りません。解雇と同様に合理性と社会的相当性が求められます。
これから試用期間を設ける場合は、就業規則に採用拒否の基準について、具体的に記載しておくとよいでしょう。
本採用拒否の手順
本採用に該当するか否かの判断は、早めに行ってください。3カ月の試用期間であれば、1カ月以内には判断する必要があります。その後に指導や教育を行うためです。
勤務態度の不良や能力が不足しているなど社員側の事情である場合、指導や教育で改善を求めます。本採用拒否を決定した場合には拒否の理由を説明し、納得を得たうえで退職を勧奨するようにしましょう。
本採用拒否になるよりも自ら退職する方が社員にとってダメージが少なく、トラブルに発展するリスクも減少します。これはあくまで勧奨であり、退職を強要するものであってはなりません。
トラブル対策におすすめの方法
採用拒否をしたあとのトラブルを避けるために、十分な指導を行ったことがわかる記録を保存していくことをおすすめします。社員の職務能力を拒否の理由にする場合は、指導をしっかり行った記録が採用拒否の合理性・社会的相当性を証明するでしょう。
最後に

試用期間は、採用する人材の適性が見極められない場合に便利な方法です。人材採用にはコストがかかるため、ようやく採用できた社員が早期離職をしてしまうことだけは避けたいでしょう。そのためにも、試用期間は有効な手段といえます。
試用期間を設ける場合は解雇や採用拒否の場合も念頭に入れ、就業規則の整備もしっかり行っておいてください。