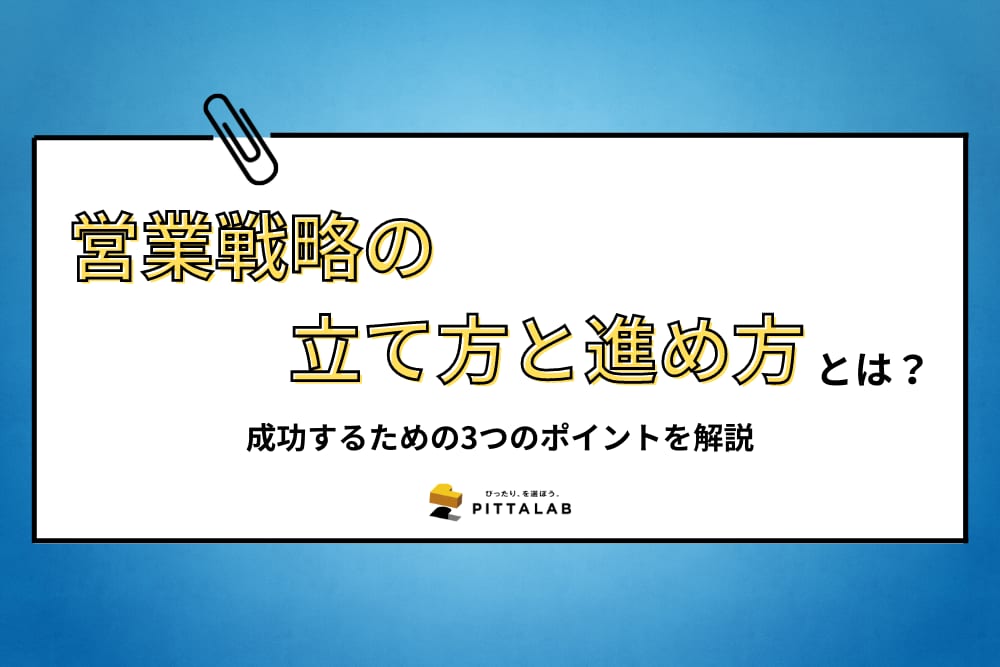「そもそも営業戦略ってなに?」「営業戦略ってどういう風にたてるの?」「営業戦略を立てる際に知っておくべき事とは?」このような疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、営業戦略についてお考えの人に向け、下記を紹介、または解説していきます。
- 営業戦略と営業戦略の意味と違い
- 営業戦略をたてる際の6ステップ
- 営業戦略を立てる際に気を付けるべきこと
- 営業戦略を成功させるための3つの秘訣
記事を読むことで、営業戦略がどういうものであり、経営活動にどう影響するものであるかを深く理解することができます。営業戦略の理解を深めることは、そのまま自社の売上げや成功につながるため、これを機にしっかりと理解しておきましょう。
営業戦略とは?

営業戦略とは、自社のサービスや製品をお客様に購入してもらうために実施する明確で具体的な施策のことです。また、営業戦略には、「企業が販売する商品やサービスの『独自性』と、他社製品との『差別化』を図る」といった意味合いも含みます。
つまり、「業界でシェア率の高い3社の売上を超えよう」「製品の質を上げて顧客満足度を上げよう」などは具体的な内容ではないため、営業戦略とは呼びません。営業戦略はあくまでも明確なものであり、企業の製品やサービスを販売するための指標(施策)である必要があります。
経営戦略や営業戦術との関係とは?
営業戦略は経営戦略と営業戦略の間に位置する概念です。経営戦略と営業戦術は次のように定義されます。
- 経営戦略:企業の継続的な成長を実現するための考え方や定義
- 営業戦術:営業戦略を実現するための具体的な手段
このように継続的な成長を目指す方針を経営戦略で固め、具体的な目標やゴールを経営戦略で、経営戦略を形にする具体的な手段が経営戦術にあたります。
個人的に取り組む方がダイエットに当てはめると、痩せる理由や痩せることで実現したいことが経営戦略、目指すべき体重やかける時間が経営戦略、そして具体的なダイエット方法が営業戦術に該当します。
基本的な営業戦略のテンプレート

営業戦略の大まかな位置づけを理解したところで、基本的なテンプレートの解説をしていきます。効果的な進め方は後述しますが、まずは目標設定、分析による現状把握、計画の立案という3つの流れを把握していきましょう。
目標設定
営業戦略の立てる際に、第一に決めるべきことが目標設定です。経営戦略で継続的な成長などの目的が定まった段階で、どのくらいを目指すべきかを模索していきます。営業戦略と聞くと攻略するための方法論になってしまいがちですが、中長期的な目標を設定することに重きをおきましょう。
分析による現状把握
分析による状況把握が、営業戦略を立てる際に決めるべき2つ目の内容です。目的はさまざまですが、営業戦略は企業をさらなる成長に導くための作戦です。そして、成長には課題の克服がつきものであり、分析による状況把握は課題を抽出するために実施します。具体的な分析内容は後述しますが、数ある種類の分析方法を試すことで、効果的な成長につながる課題を的確に抽出できます。
計画の立案
営業戦略の立てる際に、3つ目に実施すべきことが計画の立案です。目的地を決め、課題の抽出をしたら、あとはどのくらいのペースで成長していくべきかに落とし込んでいきます。「3年後に〇〇億円の売り上げを達成する」と決めると、半年後や1年後にあるべき姿が見えてきます。このあるべき姿と、課題をクリアにするペースを模索することで、営業の効率化を促進できます。
効率的な営業戦略の立て方

次に、効率的な営業戦略の立て方を解説していきます。一切の無駄なく、製品やサービスを販売するための営業戦略を立てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.中長期的な目標を立ててKPIを設定
最初のステップは、中長期的な営業目標を立て、KPIを設定することです。KPIについては下記で説明します。
中長期的な営業目標とは、「数ヶ月後、(もしくは数年後)までに目指したい会社の売上や顧客人数」といった具体的な数値目標のことです。具体的な数値目標に掲げることで、会社や社員が取るべき行動が明確になります。営業目標は、会社が成長していくうえで無くてはならないものであるといえるでしょう。
KPIとは

明確な営業目標を決定したら、次に、 KPI を設定していきましょう。KPIとは「Key Performance Indicator」 の略で、「重要業績評価指標」といいます。KPIは、営業目標を達成するために用いられる具体的な評価指数です。端的に言うと、目標達成のために必要だと仮定された具体的な数値を指します。
たとえば、「月に3本の成約を取る」という営業目標があった場合、KPIは「週に5件の新規営業開拓をする」というようなものが考えられるでしょう。ちなみに、KPIは結果や過程によって変化していくものであるため、数値を固定化させる必要はありません。この点ついては、後ほど詳しく解説します。
2.マーケットを調査
中長期的な営業目標を立てKPIを設定したら、次にマーケット調査へと移りましょう。具体的には、下記のようなことを調査します。
- 競合他社について
- 競争率の高低について
- 市場のトレンドや規模について
これらの結果を踏まえ、市場を多角的に調査していく必要があります。特に競合他社の調査は重要です。競合他社のサービスや商品を調査することで、「自社の製品にはないもの」「自社の製品が勝っているところ」などが見えてきます。
競合分析
営業戦略をより具体的なものにする、3つ目のステップが競合分析です。競合分析とは同じ市場で戦う企業が、どのような方法で売り上げを作り出しているかを観察することを指します。もちろん、圧倒的な製品やプロモーション方法で、競合に競り勝つという手段をとることも可能ですが、目指すべきビジョンを明確化することができません。自社の強みを発揮するためにも、まずは他社の戦略を把握ことが大切です。
自社分析
他社分析が終わり次第、自社分析を開始していきます。自社分析とは読んで字のごとく、自分の会社を客観的に観察することを指します。コアコンピタンスとも呼ばれ、自社ならではの強みを見出すことが最大の目的です。競合分析を終えている段階ではありますが、比較せず、自社のオリジナリティを追及していきましょう。
顧客分析
営業戦略を具体化する5つ目のステップが顧客分析です。顧客分析にもさまざま方法がありますが、まずは契約したお客様や継続的なお客様の声を整理し、共通して評価されている項目を洗い出してみましょう。そして、競合分析や自社分析の結論を重ね合わせることで、より労力を使わない、効率的な経営戦略を立案できます。
現状の課題と対応方法の策定
現状の課題と対応方法の策定も、営業戦略の立案の際に決めるべき事柄の1つです。ただし、「営業のスキルアップ」といったマンパワーを改善することではなく、ロスになっている事柄を抽出することが1番の目的である点には注意が必要です。もちろん、従業員が最低限身につけておくべきスキルを統一するといった施策も重要ですが、まずは機会ロスを減らしていきましょう。従業員に直接ヒアリングし、機能していない部分をピックアップしていくことも手段の1つです。
戦略プラン、アクションプラン策定
ここまで解説してきたステップをクリアしたら、最後に戦略プラン、アクションプランを策定していきます。環境分析や競合分析、自社分析をおこなうことで、企業が置かれている状況が明確になり、進むべき方針をクリアにできます。そして、進むべき道をどのように進んでいくかを具体化するフェーズが、戦略プラン、アクションプランの策定です。「他社が採用している方針のさらに上をいく」、「他社が〇〇という方針でシェアが高いからほかの分野で戦う」など、一社一社が異なるプランを模索していくのです。
3.顧客獲得に向け能動的に営業する
マーケットの調査を終えたら、顧客獲得に向けて能動的な営業をかけていきます。このとき、「どのような方法で商品やサービスを露出すれば顧客にウケるのか」を考えることも大切です。ただし、受動的な営業では顧客の獲得ができないため、とにかく積極的な営業をする必要があります。
受動的な営業とは、「食料品店」「ネットショップ」などのお客様を迎え入れて、商品を能動的に選んでもらう営業方法です。そして積極的な営業とは、「飛び込み営業」「ルート営業」などの、売る側がお客様の方へ出向く営業方法になります。
4.顧客のニーズを電話やSNSで把握
成果獲得の確度を上げるために、
- 顧客がサービスを実際に利用した際の反応
- 自社のサービスを利用している顧客の悩みやそれに伴うニーズ
把握しておく必要があります。また、顧客の抱える課題やニーズは、電話やSNSを利用することで、効率的に把握できます。なお、顧客の悩みを引き出すためには、相手の気持ちを理解し、共感を示すのがコツです。
たとえば、自社の商品を利用している顧客が「この商品の使い勝手はいいんだけど、継続して利用するのはちょっとねぇ……」と言われたら、こちらは「私もそう思います!継続して利用するとなると、どのようなところがネックになりますでしょうか?」という風に共感を示しつつ、悩みを引き出すとよいです。顧客が持つニーズを的確に捉えることで、実施するべき戦術が明確なものになるため、営業目標の達成率も向上します。
5.自社製品の良さを把握してクロージング
顧客が持つニーズや悩みに対し、自社製品の良さをアピールし、クロージング(顧客との契約が締結)を目指します。自社製品の売り上げがかかっているため、かなり重要なフェーズといえるでしょう。クロージングをする際のポイントは下記の通りです 。
- 相手が持つ悩みや課題を的確に捉える
- 自社製品を導入することで得られるメリットを具体的に述べる
- 自社製品の良さを押し出すだけではなく、相手に合った方法で提案する
自社製品導入のメリットを述べる際は、その根拠となる数字や具体例と共に説明する必要があります。たとえば、「弊社の製品を導入したA社は1か月で売上が○○%上がりました」などという風に伝えるとよいでしょう。
6.顧客離れを防ぐためには営業を続ける
クロージングの次に大切なポイントが「顧客離れを防ぐための営業」です。企業の売上を安定化させるためには、同じユーザーに継続して製品を購入してもらうことが極めて重要になります。継続的に製品を購入してもらうことで、営業売上が安定することはもちろん、新たなビジネス提案も可能になるのです。
たとえば最近では、サブスク(サブスクリプション)を事業の一環としてはじめる企業が増えてきています。サブスクとは、「月額で○○円支払ってもらえれば、うちの製品を使い放題にしますよ」といった、定額制サービスのことです。
このように、顧客を維持することは、新たなビジネスチャンスへとつながっていきます。新規開拓を進めることも大切ですが、「どうすれば顧客を維持できるのか」を考え抜くことも重要であることを覚えておいてください。
営業戦略で重要なフレームワークと考え方

営業戦略を効率的に進めていく上で重要となるフレームワークや考え方があります。事業を運営していくうえでは非常に重要な要素になるため、これを機にしっかりと理解しておきましょう。
基本的なフレームワーク「3C分析」

3C分析とは、市場分析をする際に活用するフレームワークです。
- Company(自社)
- Customer(顧客・市場)
- Competitor(競合他社)
それぞれの頭文字をとり3C 分析と名付けられています。3C分析を行うことで、内部(自社)と、外部(自社を取り巻いている環境)の整理に役立つでしょう。
小規模企業の武器となる「ランチェスター戦略」
ランチェスター戦略とは、「マイナーな戦場で競合他社に打ち勝つこと」を目指すための戦略です。もともとは、軍事戦略の作成に用いられていた分析モデルになります。
たとえば、大企業との争いで量の勝負になったときの勝率は低いですが、質の勝負となると、 小さい規模の企業でも勝機が見えてくるでしょう。したがって、100対1ではなく、1対1の構図を作り出すための戦略ともいえます。
新規開拓の参考にしたい「AIDMAの法則」
新規開拓を行う際は、「AIDMAの法則」を参考にするとよいでしょう。AIDMAの法則とは、「消費者の広告に対する心理的なプロセス」を描いたモデルです。AIDMAの法則が表す消費者の心理的なプロセスは下記の通り。
Attention(商品の認知)
↓
Interest(興味を示す)
↓
Desire(購買意欲が芽生える)
↓
Memory(商品覚える)
↓
Action(購入)
このような顧客の心理的プロセスを理解したうえで新規開拓を進めていきましょう。ただ最近では、SNSの拡大により、「興味を示す」からそのまま「購入」につながるケースも増えてきています。多様化した販売経路を理解しておくことも、適切な営業戦略の策定につながりますので、この動向は抑えておきましょう。
営業戦略を立てる際に気を付けること

営業活動を行う際に気をつけるべきことは下記の通りです。
- 目標は必ず明確にしておく
- 成功と失敗の両方を振り返る
- やることを決めたら行動する人物を起用
以下にて、詳しく解説していきます。
目標は必ず明確にしておく
まず、目標数値を明確に設定しておきましょう。なぜなら、目標の数値が曖昧になれば、達成に向けてやるべき行動も曖昧になるからです。また、目標の数値は結果や過程の良し悪しを反映させ、最適化することが大切になってきます。
たとえば、ひとつの成果に対して目標となる数値が低いようであれば、それを改め、高い目標に再設定することが重要になるでしょう。1件の成約に対し、50件の商談で不十分であることがデータから分かったのであれば、60件70件と増やす必要があるわけです。
成功と失敗の両方を振り返る
成功と失敗の両方を振り返るのはとても大切なことです。
たとえば、「月100万円の売上を達成する」という目標を掲げ、達成率が80%だったとき、「残り20%だから次やったら成功するだろう」という風に考えるのはよくありません。考えるべきは、「残り20%の売上を伸ばすためにするべきことは何だろう」という視点を持ち、改善していくことです。改善することを辞めてしまうと、目標達成に必要な本質を見過ごす可能性すらもあります。
そのため、営業の結果が成功であれ失敗であれ、その結果を分析し、何らかの学びを得ることが大切なのです。また、成功した時の分析をしない方が多いですが、失敗した時の分析よりも重要になるケースが極めて多い傾向にあります。
「成功の大きな要因はどこにあるのだろう」「以前は失敗したのに今回はどうして成功したのだろう」このような視点から、 成功につながった原因を追求しましょう。そうすることで、次回からも継続して目標を達成することができるようになります。
やることを決めたら行動する人物を起用
やることを決めたら、目標に向かって行動する人物を決める必要があります。実際に行動する人物を決めておかないと、責任を取る人が不明確になり、戦略の進行を遅くさせる可能性があるからです。そのため、営業戦略や目標を決めたら、誰がどのように動くかをしっかりと決めましょう。
また最近は、作業の一部を外部へ発注するケースも多く見られるようになっています。これは、行動する人物を決めるうえで、 必ず知っておきたい手法のひとつです。外部発注のメリットは下記のようなところにあります。
- 採用コストが低い
- 雑務を減らすことで社内の作業効率が上がる
- 専門家を起用することで生産性の向上に期待ができる
このようなメリットがある一方、「継続して利用すると費用がかさむ」「コミュニケーションを円滑に取れない可能性がある」などといったデメリットもあります。自社の持つ製品やサービスと、外部発注が持つメリット・デメリットを照らし合わせ、複合的に判断しましょう。
営業戦略を成功させる3つの秘訣

営業戦略を成功させるための秘訣は下記の通りです。
- 誰にでも理解できる簡単な内容にする
- KPIの数値を定期的に振り返る
- PDCAサイクルを回し続ける
以下にて、詳しく解説していきます。
誰にでも理解できる簡単な内容にする
営業戦略は、誰にでも簡単に理解できる内容にしておきましょう。なぜなら、理解しづらい営業戦略だと、企業と社員の方向性にブレが生じてしまうからです。営業戦略を作る、もしくは変更する際には下記のポイントに注意してみてください。
- 社内全体の士気が上がりやすい内容にする
- 数値を入れるなど、できる限り明確な内容にする
- 伝わりづらい文章を避け、簡潔でわかりやすい内容にする
営業戦略は社内の社員全員で取り組むからこそ強い力を発揮します。上述した3つのポイントを意識して、効果的な営業戦略を作成しましょう。
KPIの数値を定期的に振り返る
KPIの数値は定期的に振り返るようにしましょう。営業戦略や営業目標にも同じことがいえますが、設定した数値や目的のメンテナンスはかなり重要になります。
メンテナンスとは、必要に応じて軌道修正をしたり、進捗状況を確認したりすることです。特に、KPIのメンテナンスは必要不可欠になります。なぜなら、KPIの数値は、シーズンや時代の流れによっても変化する必要があるからです。
たとえば、製品やサービスによっては売れやすい季節と売れにくい季節があります。そのため、 その時折々によって、取るべき行動や目標となる数値も変わる必要があるのです。
データをもとにしたPDCAサイクルにこだわる

営業戦略や営業目標に向けて実行していくうえで、 PDCAサイクルを回し続けることはとても重要です。
PDCAサイクルとは
- Plan(計画)
- Do(実行)
Check(評価)
Action(改善)
それぞれの頭文字を取って作られた造語です。PDCAサイクルを回し続けるべき理由は下記の通り。
- 営業戦略や営業目標の見直しや改善の指標になる
- 取るべき行動が間違いだった場合の早期発見につながる
- 成果を実感できるためモチベーションが上がりやすくなる
このような理由から、営業戦略とPDCAサイクルは切っても切れない関係にあるといえます。また、Plan~Actionまでのスパンが長いと、タイムラグが生じ、有効なデータを得にくくなるため、なるべく「短く早く」を意識して回すようにしましょう。そうすることで、問題点の早期発見にもつながります。
参考にしたい営業戦略の成功事例を紹介

ここからは営業戦略を立て、成功に導いた具体的な事例を紹介していきます。今回はECサイトを有効活用したヨドバシカメラ、ファミリーレストラン市場での差別化に成功したロイヤルホストの事例を紹介します。
ヨドバシカメラのECサイト活用戦略
ヨドバシカメラはECサイトの活用戦略によって、2017年3月期に1000億円を突破する売り上げを記録した企業です。Amazonや楽天の登場によって売り上げを減らす企業が多いなか、ヨドバシカメラはヨドバシ.comと実店舗を連携させる方針を取りました。コスト削減のためにECサイトのみの運用に絞る企業が多いなかで、実店舗でもECサイトの存在をアピールするといった施策で、高い実績をあげることに成功しています。
ロイヤルホストの差別化戦略
ファミリーレストラン市場で、高級路線にシフトするという方針をとったのがロイヤルホストです。近年、低価格が主流となりつつあったファミリーレストラン市場で、ロイヤルホストは、価格帯が2000円を超えるメニューを取り揃える高級路線にシフトしました。「高いファミリーレストラン」と聞くと、マイナスイメージにつながると考えられがちですが、味や質を求める層に受け入れられ、売り上げ増を実現しています。
営業戦略への理解が深まるおすすめの本3選

最後に営業戦略への理解を深めたい人事担当者へ、おすすめの本を3つ厳選して紹介していきます。今回紹介した知識やノウハウだけでなく、本に描かれている情報にも目を向けてみましょう。
最強の営業戦略

『最高の営業戦略』はこちら
営業戦略への理解をより深められる1冊目の本が、最強の営業戦略です。この本は、世界有数の経営コンサルティングファームである、A.T.カーニーが有効と実証したノウハウを紹介した一冊です。ロジックだけでなく、具体的な例も掲載されているため、人事担当者が感じている課題をクリアするために用いられることも少なくありません。
THE MODEL
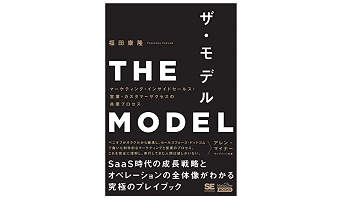
『THE MODEL』はこちら
営業戦略への理解をより深められる1冊目の本が、最強の営業戦略です。「営業職が一度は目を通しておくべき本」といわれるほどの評価を獲得している一冊です。SaaSビジネスで高い実績をもつ著者が、日米のオラクル社などで用いたノウハウを余すことなく紹介しています。
無敗営業「3つの質問」と「4つの力」
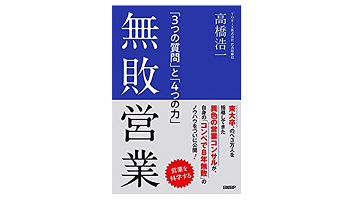
『無敗営業「3つの質問」と「4つの力」』はこちら
無敗の営業「3つの質問」と「4つの力」も、営業戦略への理解を深められる一冊です。8年もの期間をコンペ無敗という実績を持つ東大卒のコンサルタントが、ノウハウを紹介し、営業スキルの構造化をするために必要な3つの質問と、4つの力に分けて営業を科学的に紹介しています。
最後に

営業戦略は、企業の成長に必要不可欠なものであり、売上に直結する重要な指針です。そのため、営業戦略の策定にはしっかりと時間をかけることがきわめて重要になります。
ですから、企業戦略を策定する際は、記事で紹介した正当な手順を踏むことはもちろん、分析や振り返りをしっかりと行うことも大切です。営業戦略が今後の経営活動に大きく影響することを念頭に置き、 じっくりと時間をかけて策定していきましょう。