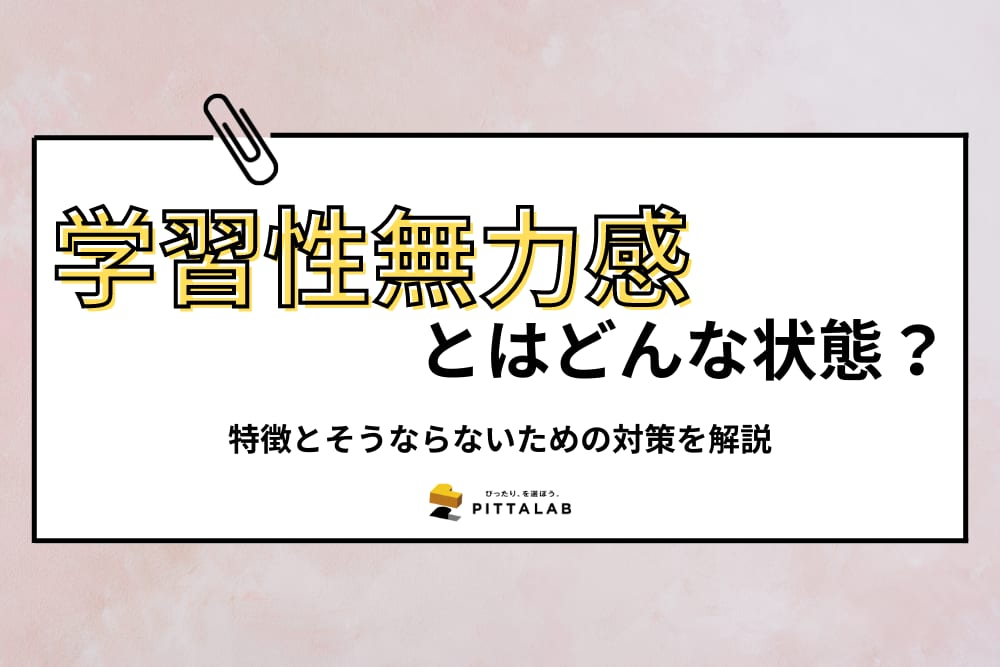「学習性無力感」とは、その名の通り無力さを学習してしまった状態のことです。こうなってしまうと抵抗さえもできなくなり、改善しようとする気力が起きなくなってしまいます。
今回は、学習性無力感の特徴やなりやすい人物像、社員が学習性無力感に陥ることを予防する方法を確認しましょう。
学習性無力感とはどのような状態のこと?

まずは「学習性無力感」がどのような状態なのかを解説します。抑うつ状態のひとつでもあるため、その点もチェックしましょう。
抵抗できないことを学習してしまった状態
学習性無力感とは、抵抗しても無力であることを学習してしまった状態のことです。嫌なことがあったとき、なんとかそれを回避できないか抵抗できないかを試す、というのが正常な動きでしょう。
しかし、抵抗や回避をしようとしても何度も対処できない状態が続いた場合に、違う反応をするようになります。「どうせ何をしても無駄」と思ってしまうようになるのです。
どうしても逃げられないと判断すると、抵抗し続けることによるさらに重大な危機が訪れることを回避するように意識が変わる、と考えられています。
抑うつ状態のひとつ
この学習性無力感とは、気力が損なわれる「抑うつ状態」のひとつでもあるのです。抵抗したほうが生命に危険があると無意識のうちに判断するため、その危険から守るために抑うつ状態になると考えられます。
これによりいくらストレスがかかって、回避したいと思っていても、その状態を変えることが難しくなってしまうのです。
なお、この抑うつ状態が常態化してしまった状態のことを「うつ病」といいます。会社でうつ病の社員を生んでしまわないように、無気力状態になっている人がいないかを確認し、フォローを行いましょう。そのフォローや予防の仕方については後述します。
セリグマン教授による実験例
セリグマン教授は学習性無力感を証明するために、犬を使った実験を行いました。まずは、下記それぞれの部屋にしばらく犬を入れておきます。
- 電気ショックが流れるが、電流の解除スイッチがある部屋
- 解除スイッチがなく、電流から逃げられない部屋
1の部屋にいた犬は積極的にスイッチを押して解除するようになったものの、2の部屋にいた犬は抵抗しても状況は改善しないままでした。
その後部屋から出し、今度は2匹とも「低い柵を乗り越えれば電流から逃げられる部屋」に入れます。すると、1の犬は柵を乗り越えて電流から逃げ、2の犬は電流を浴びたままでじっとしていました。
これは、嫌なことがあっても抵抗できていた1の犬に対し、2の犬は何をしても無駄であると思い込まされてしまったからだと考えられます。この実験により、抵抗ができない状態でストレスを感じ続けることで学習性無力感になることが証明されたのです。
学習性無力感になりやすい5つの人物像

学習性無力感になりやすい人には共通した特徴があります。その特徴とは下記の通りです。
- 内的帰属が強く自分のせいだと思いやすい人
- ミスを許さない完璧主義者
- 生活習慣が乱れている人
- アイデンティティが未確立な人
- つらい経験をしたことがある人
それぞれの人物像をチェックしましょう。
1.内的帰属が強く自分のせいだと思いやすい人
学習性無力感になりやすい特徴のひとつは、内的帰属が強く、責任が自分にあると思いやすい人です。
起こった結果の原因は何であったかの推論しやすい方向性は、人によって違います。内的帰属とは、人の内面の部分に原因があったと認識すること。反対に、社会環境や課題自体、運など、外部の要因のせいであると認識することを外的帰属といいます。
内的帰属が強い人は何かあったときに、自分のせいだ、どうせ自分が何かしても無力だ、と思い込む傾向にあるのです。そのため、外部帰属が強い人よりも学習性無力感に陥りやすくなります。
2.ミスを許さない完璧主義者
失敗を許さない完璧主義者も、学習性無力感になりやすいです。完璧主義の場合、小さなミスでさえ気になってしまうもの。一つひとつの失敗はそうたいした内容でなくても、繰り返し「ミスだ」と認識してしまうことで、無力感を味わいやすくなります。
3.生活習慣が乱れている人
生活習慣が乱れている人も、学習性無力感になりやすい人物像のひとつです。不規則な睡眠を取っていると、やる気に関係する脳内物質であるセロトニンやドーパミン、アドレナリンの分泌が足りない状態になってしまいます。
結果、やる気が起きず、学習性無力感に陥りやすいのです。
4.アイデンティティが未確立な人
アイデンティティが確立していない人も、学習性無力感になりやすい人物像に当てはまります。これは、子供の頃から親や先生の言うことばかりを聞いて、自分の意志で動けていなかった人に多いです。
大人になり自分の判断が求められるようになっても、どうすればいいのか判断できず、無力感を味わいやすくなります。
5.つらい経験をしたことがある人
今までに何かつらい経験があった人も、学習性無力感になりやすい人物像です。虐待やいじめを受けたことがあったり、裏切りを経験したりしたなどの境遇の人が当てはまります。
強いストレスを受けていると自己否定しやすい状態になり、他人への相談もしにくくなって、より悪循環に陥りやすいもの。そして、自分では良い解決法が思いつかず、学習性無力感になってしまいやすくなるのです。
社員が学習性無力感に陥ることを予防する4つの対策

社員が学習性無力感になってしまうと、やる気が出なくなったり、酷いときにはうつ病を発症してしまったりと会社にとってもダメージになります。そうならないような予防・対策の仕方を確認しましょう。
1.叱咤激励をしすぎないこと
これからもっと頑張ってほしい、と思って叱咤激励をしてしまう人も多いでしょう。余裕のある状態であれば今後の能力の伸びに繋がることではあるものの、無気力状態になってしまっている状態・なりそうな状態であれば逆効果になってしまいます。
学習性無力感になっていると、周りから見て仕事の進みが遅いように見えても、自分では頑張らなければと追い込み過ぎて、ストレスになっていることも。この状態で色々言い過ぎても、プレッシャーになってしまうばかりになります。
「どうせ無駄だ」と無気力状態になっていそうな人には、その人の良い部分を評価するような話しかけ方にして、温かい目で見守りましょう。
2.社員の意見を聞くこと
何かあったときに社員の意見を無視して話を押し通してしまうと、「どうせ話を聞いてもらえない」とだんだん無気力状態になっていきます。社員の意見を聞くことで学習性無力感の予防になるうえ、多角的な視点での意見を取り入れられるため、会社の成長に繋げられるのです。
3.以前の失敗時とは違うと理解させること
前に失敗したことがあると、「また駄目だろう」と挑戦する前から諦めてしまうことも。失敗すると思いながら仕事しても、良い発想は生まれないでしょう。
そんな時には、以前失敗した時と今回とは違うのだと伝えます。「前回より取引先との関係が良くなっている」「不満点を改善できた商品になった」「社員の意見を取り入れる社風に変わった」など、今回は前回と同じではないと理解してもらいましょう。
4.ポジティブ体験をさせること
ポジティブな考え方ができるようになると、学習性無力感になりにくくなります。そのため、ポジティブ体験をさせることで予防効果があるのです。好きなものを飲む、その日の良かったことを書く、運動するなど、良い影響のある行動をさせるようにしましょう。
なお、「どうせ無駄だろう」と考える人が多いような環境であれば、会社自体が無気力状態になっていることも。改善できない部分ではなく、改善可能な部分をどうするか考えるほうに思考の方向性を変えられるように、社内を変化させましょう。
最後に

今回は、ストレスに抵抗できなくなる学習性無力感について解説しました。無気力状態になりやすい人の特徴を知り、その人に合った予防策をして、社員がこの状態になってしまわないよう注意が必要です。
話しかけ方に注意する、ポジティブな考え方に導くなどサポートして、健全な状態で仕事ができる環境づくりをしましょう。