「パーソナルモビリティにはどんな種類があるの?」
「パーソナルモビリティを導入するメリットが期待できるの?」
パーソナルモビリティの施設内で導入を検討している企業の中には、どの種類を導入すればよいか分からずに困っている人も多いのではないでしょうか。
実は、パーソナルモビリティには2つの種類があって、導入目的に合わせて使い分ける必要があるのです。
本記事では、パーソナルモビリティの種類や導入メリット、課題、導入事例、おすすめのパーソナルモビリティを紹介します。
この記事を読んで、自社のニーズにマッチしたパーソナルモビリティを導入しましょう。
パーソナルモビリティとは

パーソナルモビリティとは、1人乗りのコンパクトな移動支援機器のことで、自転車のように中距離を移動するのに向いています。
実際にパーソナルモビリティは、CO2削減につながる新型車両として注目を集めており、国土交通省は、新しいモビリティの開発や促進を促すために、2012年に「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」を発表しました。
全国各地の調査結果によって、パーソナルモビリティは身近な移動や都市部・観光地の短距離移動においての活躍すると評価されており、国土交通省は地方公共団体にパーソナルモビリティの試行的導入を認める制度を決定したのです。
この制度によって、高速道路での走行はできませんが、市区町村ごとに協議会を設置し、地方運輸局の認定を受けることを条件に、特定地域のみでパーソナルモビリティでの走行が許可されました。
ただし、立ち乗りタイプのパーソナルモビリティは制度に含まれておらず、現在の法律では使用することはできません。
まだ日本ではパーソナルモビリティの普及は進んでおりませんが、もともとパーソナルモビリティは、歩行者と既存の乗り物の間を補完する目的で開発された移動ツールなので、海外では移動ツールとして広まっています。
今後、従来の自動車と一線を画した移動体であるパーソナルモビリティが、走行時の安全性が認められれば、パーソナルモビリティを日本全国の公道で見ることになるでしょう。
パーソナルモビリティの2つの種類

パーソナルモビリティには、大きく分けて2つの種類があります。
パーソナルモビリティの種類は以下の2つです。
- アクティビティに使える二輪タイプ
- 高齢者や山林地域に役立つ四輪タイプ
順に紹介するので、どのようなタイプがあるのかチェックしておきましょう。
(1)アクティビティに使える二輪タイプ

アクティビティに使える二輪タイプは、文字の通り2つの車輪で構成されているパーソナルモビリティです。
二輪タイプは、搭乗者が立った状態で乗り込み仕様になっており、主に体重移動で前後や左右の動きをコントロールします。
二輪タイプのパーソナルモビリティといえば、セグウェイをイメージする人も多いでしょう。
二輪なのでバランス感覚が必要で、操作が難しいと思う人もいるかもしれませんが、ハンドルがついているタイプもあり、一輪車に乗るようなバランス感覚は必要ありません。
自転車のように動き出すと安定するようになっているので、初心者でも何度か練習するだけで安全に走行することが可能です。
また、ハンドルがついておらず、車輪と足を乗せるスペースだけのものであれば、コンパクトな設計になっているので、持ち運んで歩くよりも速いスピードで移動したいときに使うこともできるでしょう。
ヨーロッパやアメリカで普及しており、今後日本でも市場が拡大することが予想されるパーソナルモビリティです。
(2)高齢者や山林地域に役立つ四輪タイプ

四輪タイプは、4つの車輪で構成されているパーソナルモビリティです。
四輪タイプのパーソナルモビリティには、立ったまま乗車するタイプのものもあれば、着席して乗車するタイプもあります。
いずれにしても、4つの車輪によって車体が支えられているので、車体の安定性がアップし、移動中に車体が転倒する心配がありません。
立ったまま乗車するタイプであれば、二輪タイプと同様に気軽に乗り降りができて、スムーズに中距離を移動することができますし、着席して乗車するタイプであれば、高齢者や身体の不自由な人でも安心して使うことができます。
二輪タイプに比べると、バランスも取りやすく安定性も増すため、走行しながら手を扱えるのも大きなメリットです。
大きな荷物を持つことや、バランスを崩したときに手で衝撃を和らげることもできるので、安全性や利便性は高まるでしょう。
二輪タイプよりも長い距離を走行するのに向いているので、安定性の高い移動手段を求めている人におすすめのパーソナルモビリティです。
パーソナルモビリティの2つのメリット

パーソナルモビリティを導入するメリットを紹介します。
今回紹介するメリットは以下の2つです。
- 高齢者や障害者の移動サポートに役立つ
- 移動手段の1つになる
順に紹介するので、どのようなメリットがあるのかチェックしておきましょう。
(1)高齢者や障害者の移動サポートに役立つ

パーソナルモビリティは、高齢者や障害者の移動のサポートに役立ちます。
四輪タイプで着席する機種であれば、立って操作する必要がないため、足腰が弱くなっている高齢者や下半身が満足に動かない障害者でも、気軽に短距離から中距離移動することが可能です。
たとえば、病院で四輪タイプのパーソナルモビリティを導入すれば、入院患者がパーソナルモビリティで院内を自分で移動することができれば、車いすで第三者がサポートする必要がなくなります。
人手不足の解消や家族などの見守りの負担も軽減されるので、高齢者や障害者の生活支援サービスとしても効果的でしょう。
もともとパーソナルモビリティは、自動車よりも気軽に移動する手段として開発されているので、今後は高齢者や障害者など歩行が困難な人向けの製品の開発が進んでいくことが予想されます。
(2)移動手段の1つになる

パーソナルモビリティは中距離移動が可能なので、単純に1つの移動手段になります。
自転車や歩きで移動するには長いけど、自動車に乗るまではいかない距離を移動するのにちょうど良いです。
二輪タイプであればコンパクトで乗り降りも簡単なので、急いでいるときに最適ですし、四輪タイプであれば座って移動できるので少し長めの距離を移動するのに適しています。
たとえば、広い敷地を有する病院やオフィスで導入すれば、目的地まで気軽に行き来することが可能です。
また、私有地内を移動するテーマパークや観光地などでパーソナルモビリティを導入すれば、利用客から人気のアトラクションとして活用できるでしょう。
観光客を集めるための方法としても有効なので、移動手段や利用客を楽しませるコンテンツを求めている企業におすすめです。
パーソナルモビリティの課題

パーソナルモビリティは、生活支援や移動手段として有効ですが、現状日本では導入する上で課題もあります。
日本では、法律上パーソナルモビリティは公道で使用することが認められていません。
イギリスを除くヨーロッパやアメリカの多くの州で公道の移動手段として認められているのですが、日本では道路交通法において、パーソナルモビリティの最適な区分が存在していないため、道路交通法の対象外となり公道での走行が禁止になっているのです。
パーソナルモビリティは、気軽に街中を走行する目的で開発され、実際にさまざまな国で導入されているにもかかわらず、日本では街中で使用することができない点が、未だに認知が進んでいない原因といえるでしょう。
しかし、日本でもパーソナルモビリティを導入している地域もあるので、近い将来パーソナルモビリティを使用できる範囲は広くなることが予想されます。
今後高齢者や障害者など歩行が困難な人向けのパーソナルモビリティの開発が進み、安全性が実証されれば、日本の公道でも使用が許可されるときがくるかもしれません。
パーソナルモビリティの導入事例10選

パーソナルモビリティの導入事例を紹介します。
今回紹介する導入事例は以下の10個です。
- セグウェイの公道走行が認められている茨城県つくば市
- セグウェイの普及活動に積極的な千葉県柏市
- 訪問支援活動に役立てた宮城県美里町
- 訪問活動や防犯活動として導入した福島県いわき市
- 観光客の利便性や娯楽性を追及して導入した兵庫県神戸市
- 公務活動の円滑化のために導入した愛媛県越智郡上島町
- 観光客の利便性の向上を目的に導入した福岡県福岡市
- エネルギー及び環境問題を解決するために導入した熊本県
- 地域住民の移動手段として導入した鹿児島県薩摩川内市
- 町中の回遊性向上のために導入した福井県大飯郡高浜町
順に紹介するので、どの地域でどのようにパーソナルモビリティが導入されているのかチェックしてみてください。
(1)セグウェイの公道走行が認められている茨城県つくば市
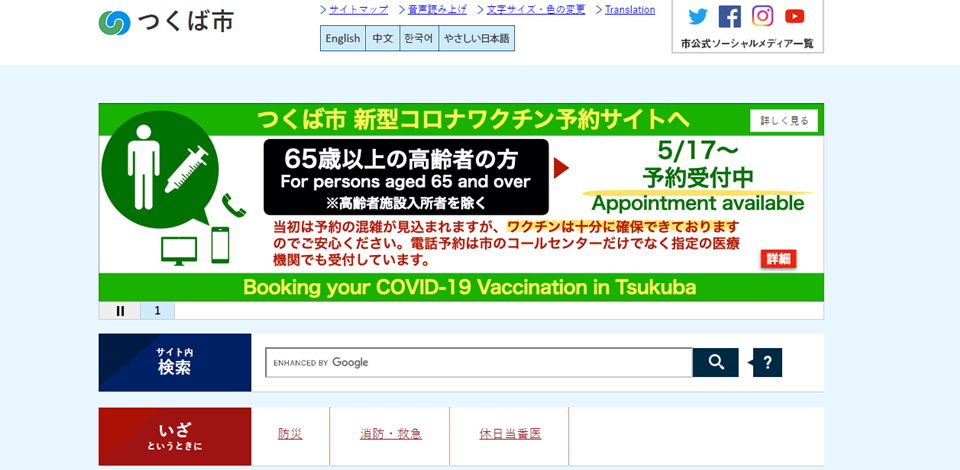
茨城県のつくば市では、セグウェイの公道走行が認められています。
2007年から「ロボットの街つくばプロジェクト」に取り組んでおり、2011年3月にモビリティロボット実験特区として認定されました。
同年6月からセグウェイなどを使った公道実験が行われるようになり、その結果公道でセグウェイを使用できるようになったのです。
日本で初めてセグウェイの公道ツアーを立ち上げ、人気観光スポットをセグウェイで回るツアーが人気を集めています。
私有地をパーソナルモビリティで走行するツアーは各地でありますが、公道を走ることができるのはつくば市だけなので、興味のある人は参加してみてください。
(2)セグウェイの普及活動に積極的な千葉県柏市
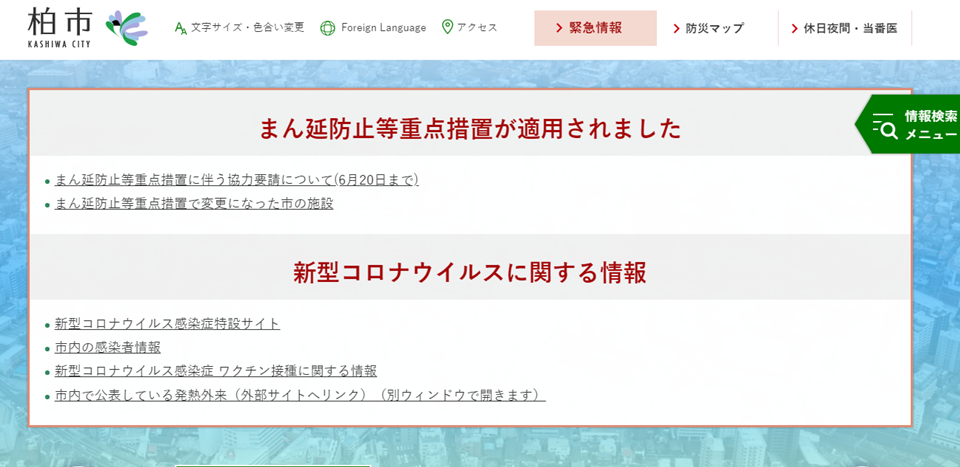
千葉県の柏市はセグウェイの普及活動に積極的です。
住民主体のサークル「柏の葉セグウェイクラブ」が、セグウェイの試乗会や柏の葉キャンパス周辺のツアーを定期的に開催しています。
柏の葉キャンパス地域はスマートシティとしての街づくりが進んでいるため、快適な移動手段になる可能性が高いパーソナルモビリティの研究や検証を頻繁に行っているエリアです。
セグウェイは街に交流を生むコミュニケーションツールとしても活躍しており、多くの人から注目を集め、活気のある街になっています。
地域密着の活動に役立つツールとしても期待されているので、町おこしを狙っている地域にもおすすめです。
(3)訪問支援活動に役立てた宮城県美里町

宮城県美里町は、パーソナルモビリティを福祉訪問業務に導入しました。
美里町健康福祉センターが、高齢者・新生児宅等への訪問支援活動を行う際の交通課題の解消やCO2削減に貢献すると判断し、美里町内の健康福祉センターを中心とした半径10km程度の行動範囲において活用することになったのです。
主に、新生児や産婦家庭訪問で子育て相談や保健指導等を行ったり、高齢者家庭訪問で介護相談や生活習慣病予防指導等を行っています。
(4)訪問活動や防犯活動として導入した福島県いわき市

福島県いわき市では、中央警察署が東日本大震災の影響を受けて仮設住宅での避難生活をしている被災者に訪問する手段としてパーソナルモビリティの導入を行いました。
小回りが効き、歩行者との親和性が高いため、防犯活動における移動手段としても活用しています。
児童に対する交通教室などでも活用されており、地域住民と近い存在になっているようです。
(5)観光客の利便性や娯楽性を追及して導入した兵庫県神戸市

兵庫県神戸市では、六甲山上の牧場や宿泊施設などにパーソナルモビリティを導入しました。
六甲摩耶山上エリアと外部をつなぐ道路は東西南北各1本ずつで合計4本のみだったため、
パーソナルモビリティの管理が容易だったこともあり、エリア内で意見が早くまとまり導入に至ったそうです。
点在する施設や観光エリア間の回遊や山頂道路のドライブ向けとして活用しており、観光客の移動に関する利便性や娯楽性を高めるだけでなく、排出ガスや騒音の削減など、環境保全を図ることもできました。
家族やカップル層など幅広い年齢層の男女が利用しているので、パーソナルモビリティは観光客が多いエリアと相性がよいといえるでしょう。
(6)公務活動の円滑化のために導入した愛媛県越智郡上島町

愛媛県越智郡上島町では、円滑に訪問活動を行うためにパーソナルモビリティを導入しました。
上島町は離島4町村が合併した合計7つの有人島と18の無人島で構成されており、3箇所の保健センターを拠点に保健師が軽自動車で保健活動を行っていました。
しかし、上島町は狭隘な道路が多数存在しており、駐車スペースも小さいので、軽自動車で移動することが不便で、スムーズに公務活動を行うことができませんでした。
そこで、軽自動車でも進入が困難な狭い道でもラクラク通れるパーソナルモビリティを導入することで、円滑な移動が可能になり、公務活動の効率がアップしたのです。
地域によっては軽自動車でも通行が難しい道があるので、移動性が不便な地域に導入すると業務効率のアップを図れるでしょう。
(7)観光客の利便性の向上を目的に導入した福岡県福岡市
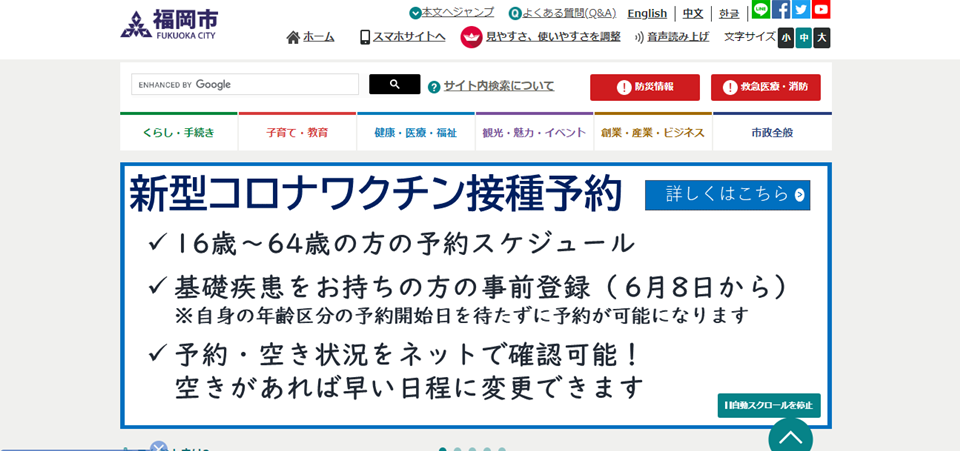
福岡県福岡市では、早良区百道浜でパーソナルモビリティを導入しました。
もともと早良区の百道浜は観光客やビジネス客が多い地域で、利便性を高めるために、観光客の観光資源やビジネス客の移動手段として、有償カーシェアリングを導入したのです。
このカーシェアリングには、スマホアプリでの予約機能や音声ガイドで観光地を案内してくれるサービスがついているので、移動手段や観光ガイドとして気軽に利用できるシステム
になっています。
地元のメディアで紹介されたことにより、利用者数が急増し、今では早良区百道浜にとって重要な観光資源といえるでしょう。
(8)エネルギー及び環境問題を解決するために導入した熊本県

熊本県は交通、エネルギー及び環境に関する課題を解決するためにパーソナルモビリティを導入しました。
公用車の利用や観光地におけるレンタカーの利用、事業者等が活用する事業用車両及び一般市民の普段利用を確認するために、一般モニター利用を実施したのです。
パーソナルモビリティを公用車として利用し、県内に周知してイメージを形成したり、観光地の有償レンタカーとして活用したりして、利便性の高さや観光振興の可能性を示唆することに成功しました。
訪問介護など事業との相性のよさもアピールできたので、今後は地域住民の移動手段や観光促進に役立てられるでしょう。
(9)地域住民の移動手段として導入した鹿児島県薩摩川内市

鹿児島県薩摩川内市は、高齢者率が40%を超える甑島に、地域住民の移動手段としてパーソナルモビリティを導入しました。
薩摩川内市は「市民の喜ぶエネルギー面での処方箋」を目的に掲げ、次世代エネルギービジョンを策定し、市内における移動や観光地を巡る手段に、エコカーの導入を目指している地域です。
また、狭い道路が多いため、コンパクトな車体のパーソナルモビリティは、省エネルギーだけでなく観光資源を巡る移動手段としても活躍しています。
(10)町中の回遊性向上のために導入した福井県大飯郡高浜町
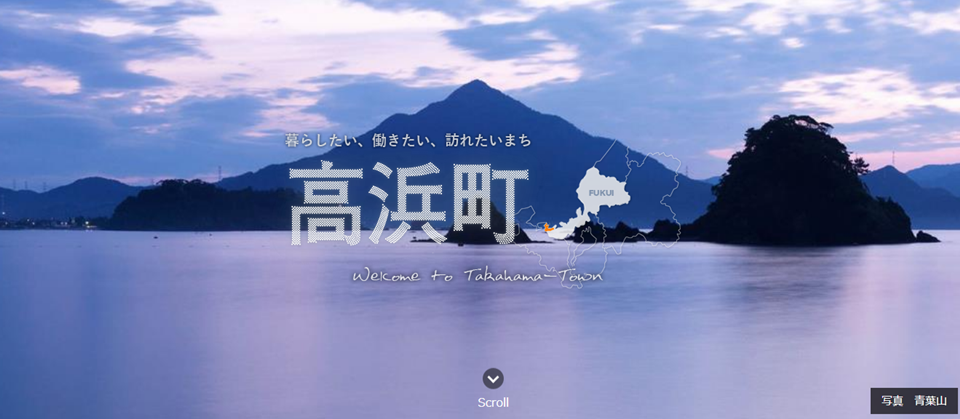
福井県大飯群高浜町では、町中の回遊性を向上させるために、パーソナルモビリティの効果検証をするために導入しました。
もともと原子力に支えられていた町でしたが、環境を支える町への転換を図っており、環境協会やシルバー人材センターなどに協力してもらい実証実験を行ったのです。
町内事業者に無料で貸与を行い、業務の一環でパーソナルモビリティを活用してもらって、町民の目に触れる機会を増やしました。
また、住民に利用してもらい、車道走行時の後続車両への影響などについても検証を行い、パーソナルモビリティの町民の認知度を広げることに貢献しました。
おすすめのパーソナルモビリティ3選

おすすめのパーソナルモビリティを紹介します。今回紹介するパーソナルモビリティは以下の3つです。
- Ninebot S-Pro(Segway Ninebot社)
- Kintone Classic(Kintone社)
- Ninebot GoKart Kit(Segway Ninebot社)
順に紹介するので、どのようなパーソナルモビリティがあるのかチェックして、製品を選ぶ際の参考にしてみてください。
Ninebot GoKart Kit【Segway Ninebot社】
Ninebot GoKart Kit(Segway Ninebot社)は、四輪タイプのパーソナルモビリティで、ハンドルを操作して移動する仕組みです。見た目はゴーカートのような形をしていますが、最大走行距離15Kmで最高速度24Km/hの性能があります。アクセルやブレーキ、ハンドルを駆使して走行するので、レーシングカートのように直感的に操作することが可能です。また、停止時にブレーキを2回踏むことで後退モードとなり、簡単に車体をバックすることができます。
バッテリーの減りを調節することも可能で、使用するシーンや移動距離に合わせて電源モードを変更できる点も便利です。クッション性が高い中空タイヤ衝撃から守ってくれるフロントバンパーが搭載されているので安全性も高く、繰りたたみ式でセダンタイプの車のトランクにも積めます。アトラクションとして子どもを中心に人気を集められるので、私有地内を巡るツアーなどにおすすめのパーソナルモビリティです。集客目的でパーソナルモビリティを活用したい企業や地域は、前向きに導入を検討してみてはいかがでしょうか。
- 価格
- 73,800円 (税込)
- 種類
- 四輪タイプ
- 本体サイズ(幅×高さ×奥行)
- 1383x822x600(mm)
- 走行距離
- 最大15km
- 最高速度
- 24km/h
- 充電時間
- 要問合わせ
Kintone Classic【Kintone社】
Kintone Classic(Kintone社)は、ハンドルが付いていない二輪タイプのパーソナルモビリティで、体重移動だけで操作する仕組みです。最初は怖いかもしれませんが、慣れてくると魔法のように前に進むため、体験したことのない経験をすることができます。電気用品安全法で認められている製品なので、過充電による発火の心配はありません。キックボードのような感覚で遊具として活用している家庭も多く、親子で楽しめるパーソナルモビリティです。
そのため、子どもだけでなく大人も楽しめる乗り物なので、ツアーなどのアトラクションとして導入するとよいでしょう。また、気軽に移動するための手段としても最適なので、さまざまな用途に対応しているパーソナルモビリティといえます。金額も3万円代とリーズナブルなので、パーソナルモビリティの導入コストを抑えたい企業におすすめです。
- 価格
- 32,780円 (税込)
- 種類
- 二輪タイプ
- 本体サイズ(幅×高さ×奥行)
- 580×180(mm)
- 走行距離
- 最大10km
- 最高速度
- 約10km/h
- 充電時間
- 3~4時間
Ninebot S-Pro【Segway Ninebot社】
Ninebot S-Pro(Segway Ninebot社)は、二輪タイプのパーソナルモビリティで、ハンドルはなく脚と身体の重心移動だけで操作する仕組みになっています。1回の充電で30kmの長距離移動ができ、走行データを収集してくれるので、車体を調整しながら高い安全性で簡単に操作することが可能です。軽量でコンパクトな設計になっているため、車のトランクに入れて持ち運びすることもでき、飛行機にも利用されているマグネシウム合金をフレーム素材に採用していることから、頑丈なボディになっています。
また、感応式LEDライトが搭載されているため、周囲の明るさによってライトの強さを自動調節し、周囲に存在をアピールすることもできるのです。専用アプリでラジコンのように遠隔操作することも可能で、LEDライトのカラーのカスタマイズなどさまざまな設定ができるので、使い勝手は高いといえます。公道では使用できないため、私有地内の移動手段としてパーソナルモビリティの導入を検討している企業は、試しに使ってみてください。
- 価格
- 79,800円 (税込)
- 種類
- 二輪タイプ
- 本体サイズ(幅×高さ×奥行)
- 262×546×611〜866(mm)
- 走行距離
- 約30km
- 最高速度
- 約18km/h
- 充電時間
- 約4時間
まとめ

パーソナルモビリティを導入することで、移動のスムーズ化や生活支援のサポートなどさまざまな効果が期待できます。二輪や四輪だけでなく、ハンドル付きや着席するタイプなどさまざまな種類があるので、用途に合わせて選ぶことが重要です。今回紹介した導入事例やおすすめのパーソナルモビリティを参考にして、自社のニーズにマッチした製品を導入しましょう。






